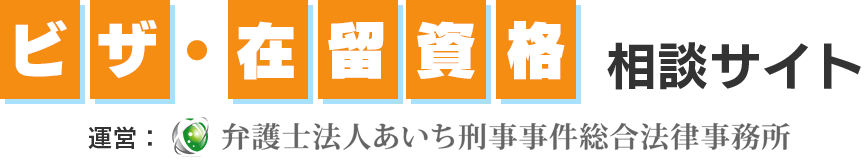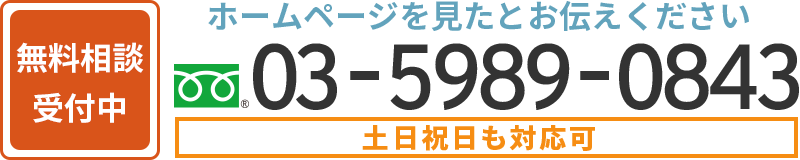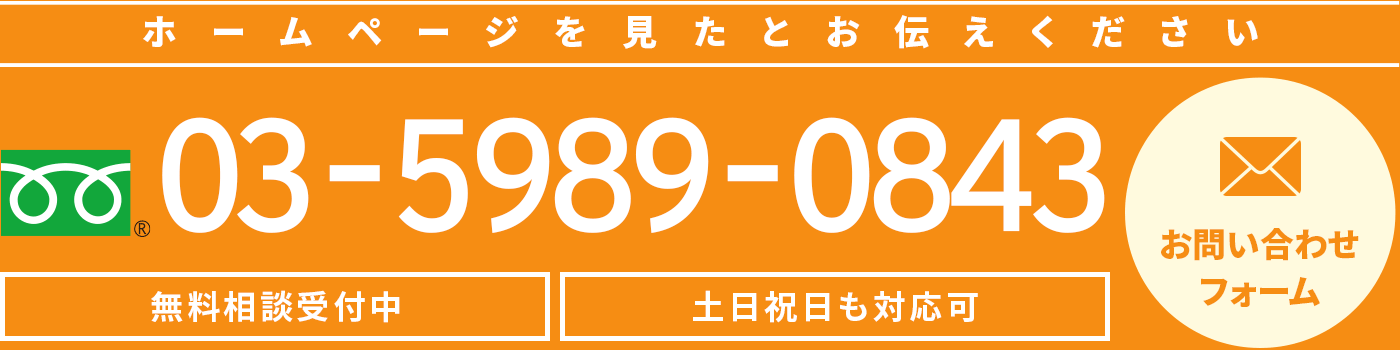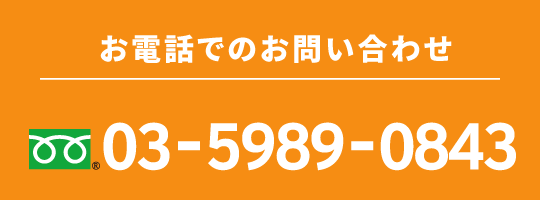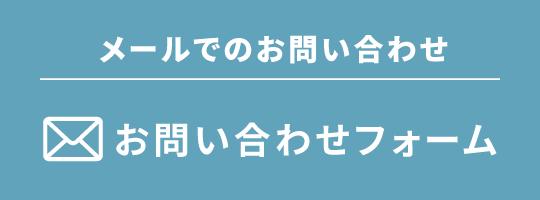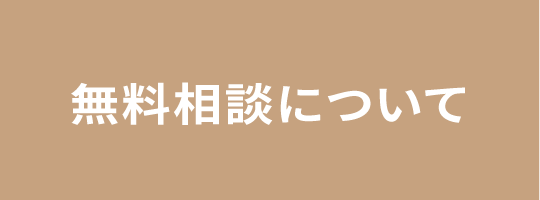弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が外国人が日本で働くために必要な「就労資格」について解説します。
外国人が日本で働くために必要な就労資格は、入管表別表第一の上覧の在留資格(活動資格)一の表と二の表にあげられています。
当ブログでは、入管法別表第二の表のうち「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」について、
対象職種・業種、取得条件、在留期間、その他要件・注意点について解説します。
二の表(就労資格、上陸基準の適用あり)
このページの目次
教育(Instructor)
主な対象職種・業種: 小学校・中学校・高等学校等の教員、専修学校・各種学校の教師、語学指導助手(ALT)など。インターナショナルスクールの教師等も含まれます。
取得条件: 原則として大学卒業以上の学歴、または教員免許状等その教育職に必要な資格を有すること。
語学(外国語)教師の場合は、教えようとする外国語により12年以上教育を受けたことが必要です。
雇用先となる教育機関からの雇用契約が必要です。
在留期間: 5年、3年、1年又は3か月
その他: 「教育」ビザは大学相当未満の教育機関での教職が対象であり、大学で教える場合は「教授」ビザとなります。
また企業経営の英会話学校等で働く場合はこの在留資格ではなく「技術・人文知識・国際業務」が適用されます。
技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
主な対象職種・業種: いわゆる一般的なホワイトカラー職種が幅広く該当します。
例えばシステムエンジニア、プログラマー、通訳・翻訳、貿易営業、マーケティング、デザイナー、語学講師(民間語学学校)など多岐にわたります。
理工系・人文系の専門知識や国際業務スキルを活かす職種が対象です。
取得条件: 学歴要件として「業務に関連する分野の大学卒業(学士)以上又はこれと同等の教育を受けたこと。」「業務に関連する分野の専修学校の専門課程を修了したこと。」または職歴要件として「実務経験10年以上」が基本条件です。
。近年の制度緩和により、日本の専門学校を卒業し「専門士」「高度専門士」の称号を得た場合も関連業務で就労ビザ取得が可能となりました。
。職務内容と専攻分野との関連性が重視され、かつ給与水準が日本人と同等以上である必要があります。
在留期間: 最長5年(通常1年または3年での更新。更新回数に制限なし)
その他: 就労資格の中で日本で働く外国人に最も利用されている在留資格です。
製造業のライン作業や単純労働は認められず、あくまで専門知識・技能を要する職種に限られます。
専攻と職務のミスマッチがある場合は不許可となるため、採用時には職務内容の適切性に注意が必要です。
企業内転勤(Intra-company Transferee)
主な対象職種・業種: 外資系企業や多国籍企業の社員が、本社・支社間の人事異動で日本に一定期間赴任して働くケースが該当します。
。例えば海外の親会社・子会社から日本支店へ転勤してくる社員などが代表例です。
職種としては上記「技術・人文知識・国際業務」に該当するような専門的業務(技術者、管理部門スタッフ等)が中心です。
取得条件: 転勤前に海外の本店・支店等において少なくとも1年以上継続勤務していること。
日本で従事する業務が、転勤元で行っていた業務と同種であること(専門的分野の業務)も条件です。
転勤元・転勤先企業の資本関係(親子会社・支店関係)が明確である必要があります。
在留期間: 5年、3年、1年等(更新可)。
その他: 日本法人での雇用契約は不要で、在籍会社からの派遣という形になります。
同一企業内の異動であるため、学歴や職歴の要件は問われません(1年以上の勤務実績が要件となります)
介護(Nursing Care)
主な対象職種・業種: 介護福祉士として介護施設や病院等で介護業務に従事する介護士。高齢者介護施設の介護職員などが該当します。
取得条件: 日本の国家資格である介護福祉士の資格取得者であること。
通常は日本の介護福祉士養成施設を卒業し国家試験に合格するか、EPA(経済連携協定)による来日後に試験合格することで資格を得ます。
法律上日本語能力の明確な基準はありませんが、介護福祉士資格取得には専門学校入学時点でN2程度の日本語力が事実上必要であり、利用者とのコミュニケーションにも必須なため実際には日本語能力試験N2相当以上が望まれます。
在留期間: 5年、3年、1年等(更新可)
その他: 同じ介護分野でも「特定技能(介護)」やEPA介護候補者とは異なる在留資格であり、要件も大きく異なります。
(特定技能は資格不要・N4程度の日本語で可だが介護ビザは有資格者のみなど)。資格維持のため業務に就き続ける必要があり、介護職以外の仕事はできません。
興行(Entertainer)
主な対象職種・業種: 芸能やスポーツ分野で報酬を得て活動する者が対象です。
例えば俳優、歌手、ダンサー、演奏家などの芸能人やプロスポーツ選手、モデル等が該当します。
興行イベントへの出演者や、それに付随する重要なスタッフも含まれる場合があります。取得条件: 日本で行う興行(公演・興行イベント)に関する契約があることが前提です。
申請人本人に関する要件として、外国の教育機関で当該芸能活動に関する科目を2年以上専攻しているか、または外国で2年以上の実績(経験)があることのいずれかを満たす必要があります。
。また受け入れ機関(招聘元)に関する要件として、興行主に十分な経営基盤があることや報酬が適正であること等が審査されます。
在留期間: 最長3年(活動内容に応じて1年や3ヶ月など短期の許可も多く契約期間に合わせて在留期間が決定されます。)
その他: 興行ビザでは契約された興行活動以外での収入活動は認められません。興行内容によっては風俗営業法等他法令の遵守も求められます。
興行ビザには細かい区分があり(興行1号・2号など)、活動内容ごとに要件が定められています
技能(Skilled Labor)
主な対象職種・業種: 調理師(外国料理のシェフ)、ソムリエ、宝石・貴金属加工職人、衣料・織物職人、家具工芸職人、動物調教師、スポーツ指導者・トレーナー、航空機パイロットなど熟練した技能を要する職種。
日本には少ない特殊技能(例えば各国料理の調理など)に従事する外国人が対象です。
取得条件: 職種ごとに定められた相当年数の実務経験や資格が必要です。多くの場合少なくとも3~10年以上の実務経験が求められます。
例えば外国料理のコックは通常10年以上の調理実績が必要ですが、タイ料理人の場合は一定の技能証明書と直近1年の本国での調理経験があれば5年の経験でも認められる特例があります。
このように職種により要件が異なるため、事前に各技能分野の基準を確認する必要があります。
在留期間: 最長5年(更新可能。通常1年または3年ごと)
その他: 対象となる技能職種は法律で限定的に列挙されています。
技能実習を経て培った技能を実務として活かすケースもあります。技能ビザで認められる範囲外の単純労働はできません。また、日本人と同等以上の報酬が支払われる必要があります。
特定技能(Specified Skilled Worker)
主な対象職種・業種: 人手不足が深刻な産業分野における即戦力労働者を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、現在16分野(外食、介護、建設、農業、製造業など計16産業分野)で受け入れが可能です。
取得条件: 特定技能1号(中級技能者)と2号(熟練技能者)に分かれます。
1号は各分野ごとの技能試験及び日本語試験(一般に日本語能力試験N4相当)に合格することが必要です。
一方、特定技能2号は1号修了者等でさらに熟練した技能を持つ人が対象で、より高度な試験合格や実務経験が求められます。
在留期間: 1号は通算で最長5年まで(1年・6ヶ月等の在留を更新、合計5年で上限)
2号は在留期間の上限はなく、継続的に更新可能です(在留期間は最長3年までで更新回数無制限)
その他: 1号では家族の帯同は原則不可ですが、2号になると配偶者や子の帯同が認められます。
特定技能制度は技能実習で培った人材の受け皿としての側面もあり、技能実習からの移行も可能です。人手不足解消を目的とした制度のため、
待遇は日本人同等以上とすることや支援体制の整備(1号の場合、登録支援機関による支援が必要)などの条件も付されています。
技能実習(Technical Intern Training)
主な対象職種・業種: 開発途上国等の外国人が日本で技能移転を受けるための実習生制度です。海外の子会社から受け入れる企業単独型実習生や、送出機関・監理団体を通じて受け入れる団体監理型実習生が対象となります。
。職種は農業、建設、製造業など多数(91職種)168作業が指定されており、日本の企業等でOJTを通じ技能を習得します。
取得条件: 自国の送出機関などを通じ、日本の受入企業と技能実習契約を結ぶ必要があります。
入国時は技能実習1号(原則1年)から開始し、所定の試験合格など要件を満たせば2号・3号へと段階的に移行して最長5年間の実習が可能です。
各段階で技能検定の合格など一定の成果が求められます。また実習終了後は原則として習得技能を活かすため帰国することが前提ですが、優良修了者は特定技能への移行も認められています。
在留期間: 最長5年(技能実習1号=1年以内、2号=2年、3号=2年の合計)
通常は1年ごとに在留資格更新・段階変更しながら進みます。
その他: 技能実習は労働力の受入れではなくあくまで国際貢献・人材育成を目的とする制度です。
そのため転職や実習職種の変更はできず、実習計画に沿った業務のみが許可されます。近年制度見直しの動きもあり、2027年以降「育成就労」へ一本化検討されます。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、日本で働ける就労資格の中から「教育」「技術・人文・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」について、対象職種・業種、取得要件、在留期間、その他の要件・注意点について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の就労資格に関する在留申請手続きを取り扱っております。
日本で働きたい外国人の方や外国人の採用をお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。