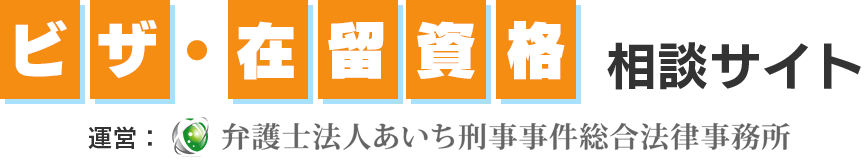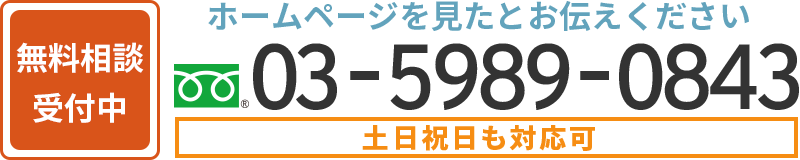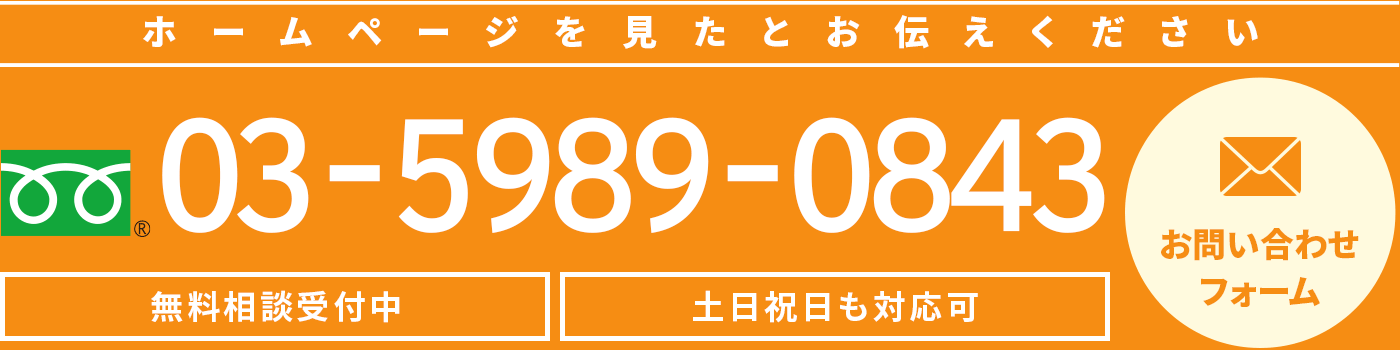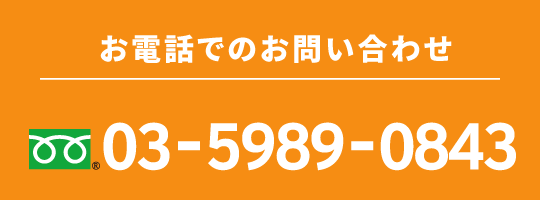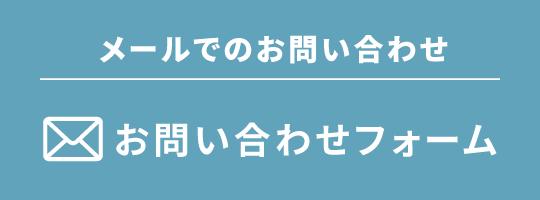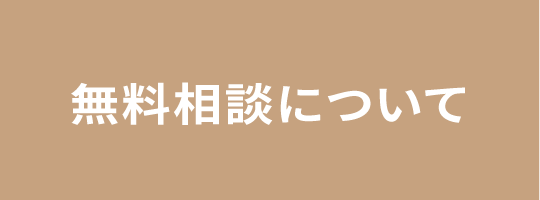Author Archive
上陸拒否の特例とは何か?再入国が認められる?

上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
日本に入国を希望するも上陸拒否となり入国できないケースが存在します。
しかし、特別な条件下での特例があり、上陸拒否に該当していても入国が認められる場合もあります。
今回はAさんの事例をもとに、上陸拒否の特例について詳しく解説します。
1.上陸拒否とは何か?
日本に入国を希望する外国人が増える中、日本滞在中にオーバーステイや何らかの犯罪をして裁判所で有罪判決を受け強制送還の処分となると,5年又は10年の上陸拒否や犯罪の種類により無期限上陸拒否といった,日本への再入国が拒否されるケースがあります。
「上陸拒否」とは、特定の理由により、外国人が日本に入国することを許可されない状態を指します。
しかしながら一定の条件で上陸拒否を免れる「特例」が存在します。
例えば、家族の結合等の人道上の理由、日本での在留状況等で、特定の条件を満たす場合等です。
ここでは上陸拒否の基本的な概念と、それに関連する特例についての概要を説明します。
2.Aさんの事例紹介
Aさんは、20年以上日本に在住している定住者で、日本に仕事があり家族がいます。
彼は子供の頃に生まれた国から両親と日本に来て、日本の小、中、高で学んできました。
高校を卒業してからは,地元の大手メーカーへ就職しました。Aさんはこれまでの人生の大半を日本で過ごしてきました。彼の本国には知りあいがおらず、彼の友人は全員が日本に住んでいます。
ある日、Aさんは友人から受け取った大麻草を公園で吸っていたところを警察に発見され、逮捕されました。逮捕後、裁判所に起訴をされて執行猶予付きの有罪判決を受けました。
判決後、Aさんは在留更新を行いましたが更新は認められませんでした。
更新不許可後、Aさんは在留期間内に自主的に帰国しました。帰国して1年後日本への再入国を試みましたが、入国拒否となりました。
Aさんは、家族や仕事、失った日本での生活全てを取り戻すため、上陸拒否の特例を求める手続きを開始しました。
3.入管法の規定について
入管法第24条には、上陸を拒否される外国人の具体的な事由が列挙されています。これに該当する場合、原則として日本への入国は許可されません。
薬物事犯、不法入国、不法滞在、偽造・変造された旅券の使用など、多岐にわたる事由が上陸拒否の理由として挙げられています。
しかし、入管法には上陸拒否の特例に関する規定も存在します。特定の条件を満たす場合、法務大臣の裁決により、上陸が特別に許可されることがあります。
上陸拒否の特例を受けるためには、許可を認めてもらうだけの「相当の理由」が必要とされます。
この「相当の理由」には、家族との結びつきや、人道上の理由(日本での申請人の生活基盤、申請人や配偶者の健康状態など)が含まれます。
上陸拒否の特例を求める場合、関連する書類や証明資料を提出し、法務大臣の裁決を受けるプロセスを経る必要があります。(出入国及び難民認定法第5条のニ)
上陸拒否の特例の中でも、人道上の特別な事情は、上陸拒否の特例を認めるうえで重要なポイントとなります。
Aさんのケースでは、日本での滞在歴の長さや日本への定着性、本人の反省度、家族との結びつきなどが、人道上の特別な事情として考慮される要因となります。
4.再入国の方法について
上陸拒否を受けた外国人が日本に再入国するための手段として、在留資格認定証明書を通じた方法があります。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に在留するための資格を有していることを証明する書類です。
この認定証明書を取得することで、再入国の際の上陸審査がスムーズに行われる可能性が高まります。
5.まとめ
上陸拒否事由に該当する事は、再入国するにあたりとても大きな障壁となりますが、上陸拒否の特例に必要な要件を満たすことで、この障壁を乗り越えることが可能です。
上陸拒否の特例を受けるためには、多くの証明書類の提出が必要となります。
上陸拒否の特例のプロセスは大変複雑であることから、是非入管業務の専門家のサポートを得ることをお勧めします。当事務所でも上陸特別許可に関するご相談はこちらから受け付けています。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
定住者の「素行善良要件」とは何か

定住者の「素行善良要件」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
在留資格「定住者」を取得又は更新する際に重要な審査要件一つが「素行善良要件」です。
この記事では、「素行善良要件」が具体的にどのようなものなのか、そしてそれがどのように在留資格に影響するのかを事例を交えて詳しく解説します。
定住者の在留資格とは?
定住者の在留資格は、日本で安定して長期間滞在するための資格の一つです。
この資格にはいくつかの種類があり、それぞれに独自の要件が設定されています。
例えば、日系3世やその配偶者、日本人の子として出生した者の実子などが対象となる場合(告示定住),日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き日本に在留を希望する者が対象となる場合があります。(告示外定住)
定住者の在留資格を取得又は変更・更新するためには、いくつかの審査要件をクリアする必要があります。
その中でも重要なのが「素行善良要件」です。
「素行善良要件」とは何か?
「素行善良要件」とは、在留資格「定住者」を取得又は変更・更新する際の審査要件の一つです。
具体的には、以下のような状況が該当します。
日本国または他の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金などに処せられたことがない。
少年法による保護処分が継続中でない。
日常生活や社会生活で、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していない。
他人に不正な行為を行ったり、不法就労のあっせんを行っていない。
つまり,法律や社会規範に反するような言動が無いことを言います。
この「素行善良要件」が満たされていないと、定住者の取得又は変更・更新が認められない可能性が高くなります。
素行善良要件の審査基準
素行善良要件の審査には、出入国在留管理局が設定したガイドラインがあります。
このガイドラインに基づき、以下のような点が評価されます。
過去の犯罪歴: 日本国内外での法令違反が評価されます。
現在の生活状況: 違法行為があるかどうか。
審査はケースバイケースで行われるため、一概には言えませんが、上記のような点が総合的に評価されます。
以下の事例で素行善良性について考えてみましょう。
事例1:スピード違反での逮捕・起訴
スピード違反で逮捕・起訴された場合、この場合は「素行善良要件」に大きな影響を与える可能性があります。
特に、逮捕・起訴が繰り返されると、その都度、在留資格の取得や更新が困難になる可能性が高まります。
逮捕・起訴された場合、以下のような影響が考えられます。
在留資格の取得: 新規で在留資格を取得する際、素行善良要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。
在留資格の変更・更新: 既に在留資格を持っている場合でも、更新時に再度審査が行われ、素行善良要件を満たしていないと判断されると、更新が認められない可能性があります。
このような状況を避けるためには、法令を遵守し、交通ルールを遵守し交通違反で検挙されないよう注意を払う必要があります。
事例2:スピード違反での反則金
スピード違反で反則金を支払った場合でも、これが「素行善良要件」に影響を与える可能性があります。
ただし、反則金の場合は逮捕・起訴されるケースよりも影響は軽微であることが多いです。
具体的な影響は以下の通りです。
在留資格の取得: 反則金を支払った場合でも、その他の素行善良要件がしっかりと満たされていれば、新規での在留資格取得は可能です。
在留資格の変更・更新: 既に在留資格を持っている場合、反則金の支払いが一度か二度程度であれば、更新時の審査に大きな影響はないとされています。
しかし、反則金の支払いが繰り返されると、その都度「素行善良要件」の審査で不利に働く可能性があります。
「素行善良要件」は、定住者の在留資格を取得または変更・更新する際に非常に重要な要素です。
事例を交えて説明しましたが、スピード違反などの法令違反を繰り返すと、この要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。
特に逮捕・起訴された場合や反則金の支払いが繰り返されると、在留資格の取得や変更・更新が困難になる可能性があります。
普段の生活では法令を遵守し、社会的に非難されるような行為を避けることが重要です。
「定住者」の在留資格について取得,変更,更新にお困りのことがある方は,こちらからお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
「経営・管理」のビザがとりやすくなった?

在留資格「経営・管理」の取得要件緩和について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
出入国在留管理庁は、外国人の起業を増やすために2024年度中に、「経営・管理」在留資格の要件に関する省令を改正する予定です。
日本国民や永住者、日本人の配偶者などの在留資格があれば、国内で自由に会社の経営や役員職につくことができますが、外国人は在留資格に応じてこれらの職に就くことについて制限されています。
「経営・管理」の在留資格とは、外国人が日本で会社経営や管理職として勤務ができる在留資格であり、以前は「投資・経営ビザ」として知られていましたが、現在では外国の資本が関与していなくても取得が可能となったため、名称が「経営・管理ビザ」に変更されています。
通常、「経営・管理」の在留資格での在留期間としては、3ヶ月から5年までの間の複数の期間が設定されていますが、申請者の提出した計画や状況により在留期間は決定され、初回では1年間が標準的な期間となっています。
外国人が「経営・管理」の在留資格を取得した場合、基本的には1年更新の在留資格であるため、原則として1年ごとに在留期間の更新手続きが必要になります。
「経営・管理」の在留資格の取得要件として、①独立した事業所の確保、②500万円以上の出資金又は2名以上の常勤職員の雇用、③事業の安定性・継続性が求められます。
以下、各取得要件についてご説明いたします。
・事務所の確保
「経営・管理」の在留資格を取得して日本で会社を設立するためには、事務所を確保する必要があり、「経営・管理」の在留資格を取得するには、独立した事務所が必要です。
事務所ごとに明確な仕切りがないバーチャルオフィスやレンタルオフィスでは事務所としては認められず、また原則として、自宅として利用しているアパート、マンションなどを事務所とすることもできません。
・事業規模の要件と安定性,継続性
「経営・管理」の在留資格を取得するためには、「経営・管理」の在留資格を取得する外国人本人による500万円の出資金又は日本に居住する常勤職員(日本人、特別永住者、日本人の配偶者、永住者等)を雇用するなどの事業規模が必要です。
設立する会社の事業に適正性、継続性と安定性があることも求められます。
事業内容や収支見込み、事業計画書などを提出して、適正性、継続性と安定性を示します。
ビジネスの実体があり、利益をだし事業継続できるのかという点について審査されることになります。
したがって、何年にもわたって赤字を出し続けることが想定される会社は認められません。
2024年度に独立した事業所の確保及び500万円以上の出資金の要件の緩和、在留期間が1年から2年への延長が予定されています。
また、在留期限の更新に際しても、一般的には毎年の更新が見込まれていますが、運営する事業経営状況や経営者の在留履歴、事業の規模、素行などに応じて、更新期間を2年や3年と延長することが許されるケースも存在します。
日本で会社を経営するために取得する「経営・管理」の在留資格では、学歴や職歴要件は要求されていませんが、誰でも申請ができる反面、日本で会社経営ができるのかという、事業規模と事業計画の面が厳しく審査されることになります。
2024年度の改正により、経営管理の在留資格取得の要件が緩和されると言われています。
具体的には、以下のように各取得要件が緩和がされる改正が予定されています。
従来は原則1年の在留期間であったのに対して、2年間に延長される予定です。
また、日本国内の独立した事業所の確保という要件についても、大学の研究室の一部などに拠点を設置する方法でも可能とされる予定です。
さらに、500万円の出資金又は2名以上の常勤職員の採用という要件についても、出資金なしでも可能とされる予定です。
これらの改正が実現されると、今まで認められなかった共同事務所での間借りやシェアオフィスでの事業所利用なども可能となります。
以上のように、外国人が起業しやすい環境をつくることで外国人起業家を増やしていく方向性が示されましたので、今後の法改正について注目が必要となります。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
「技術・人文・国際業務」の在留資格

日本には日本で働く外国人のために多くの就労資格がありますが、その中でも特に「技術・人文・国際業務」の在留資格は多くの日本で働く多くの外国人に選ばれています。
この記事では、「技術・人文・国際業務」の特徴、活動内容、審査基準などを事例を交えて詳しく解説します。
当サイトでも,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について解説をしています。
「技術・人文・国際業務」の在留資格とは?
在留資格の概要
技術・人文・国際業務の在留資格は、日本で働く外国人が取得することのできる就労資格の一つです。
この在留資格は、特に高度な専門性を持つ外国人が対象となります。
対象となる人
この在留資格は、日本の大学や専門学校に留学している留学生、または特定の専門性を持つ外国人が対象となります。
例えば、エンジニア、研究者、ビジネスマンなどが該当します。
日本で働くには、在留資格が必要です。
特に、この「技術・人文・国際業務」の在留資格は、高度な専門性が求められる職種で働く際に必要となります。
活動内容について
①理学、工学などの自然科学分野
この在留資格では、理学や工学などの自然科学の分野での活動が認められます。
具体的には、研究開発、製造技術、品質管理などが含まれます。
②法律学、経済学などの人文科学分野
法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野でも、この在留資格での活動が可能です。
例として、法律コンサルタント、経済アナリスト、社会研究者などが考えられます。
③国際業務における活動分野
国際業務においても、この在留資格は適用されます。
具体的には、国際貿易、外国市場調査、国際プロジェクトマネジメントなどが該当します。
この在留資格で認められる活動内容は多岐にわたりますが、共通して高い専門性が求められる点が特徴です。
活動内容と審査の基準
出入国管理及び難民認定法に基づく基準
この在留資格の審査は、出入国管理及び難民認定法に基づいて行われます。
この法律には、在留資格を取得するための一定の基準が明示されています。
審査におけるポイント
審査では、申請者の専門性、経験、そして日本での活動内容が重要なポイントとなります。
具体的には、以下のような要素が評価されます。
専門的な資格やスキルの有無、過去の実績や経験、日本での活動計画とその実現可能性等です。
審査においては、申請者自身が高い専門性と実績を持っていることを資料を基に証明する必要があります。
在留資格取得のポイント
専門性と経験を明確に証明する資料が必要です。各種の申請書はこちらからもダウンロードできます。
日本での活動内容とその実現可能性が求められます。
日本でのサポートする組織や企業からの採用通知書が求められます。
注意すべき事項
在留資格の更新や変更には、早めに手続きを始めることが必要とされます
在留資格がない状態での活動は違法となるため、絶対に避ける必要があります
専門性や経験を高めるための継続的な学習とアップデートが必要となります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてお困りのことがある方は弊所までご相談ください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
ベトナム国籍の人との国際結婚とその手続き

「ベトナム人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
1.ベトナムと日本の婚姻制度の違い
日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたが、ベトナムでの結婚可能年齢は、男性20歳、女性18歳です。
日本では離婚や死別から100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、ベトナムにおいては、女性に対して再婚禁止期間の定めはありません。
ベトナム人と日本人の国際結婚の手続きは、先に日本で結婚手続きを行うか、先にベトナムで結婚手続きを行うかによって変わってきます。
特に、ベトナムは社会主義国ですので、日本と比較して国家が国民生活に対して干渉する度合いが大きいです。
ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。
2.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
まずは、ベトナム人に関する婚姻要件具備証明書(独身証明書)を、在日ベトナム大使館で発行してもらう手続きを行います。
その際の必要書類は、下記の通りです。
【ベトナム人が用意する書類】
・現住所証明書
・出生証明書
・婚姻状況証明書
・人民証明書(人民委員会が発行)
・パスポート(原本)
【日本人が用意する書類】
・パスポートの写し
・住民票
ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を受領したら、日本の市区役所等で婚姻届を提出します。
日本の市区役所等で婚姻届提出する際は、2人で手続きを行ってください。
その場合の必要書類は、下記の通りです。
・ベトナム人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(本籍地の役所・役場に届け出る場合は不要)
日本の市区役所等で婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書を受領します。
その後、戸籍が変更されたら戸籍謄本を取得して、在日ベトナム大使館に対して「報告的届出」を行います。
その際の必要書類は、下記の通りです。
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポートの写し
3.ベトナムで先に結婚手続を進める場合【ベトナム先行方式】
まず、日本の地方公共団体に相当する「人民委員会」にて婚約申請を行います。
「人民委員会」にて婚約申請を行った後に、法務局で面接の予約を行います。
そして、法務局から指定された日時に面接を受けた後に、結婚登録が行われます。
その際に必要な書類は、下記の通りです。
【ベトナム人が用意する書類】
・人民証明書(人民委員会発行のもの)
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(法務局発行)
・精神科医の健康診断書(ベトナム公立病院の医師発行)
・HIVなど感染症に関する診断書(保健所発行)
・パスポートの写し
結婚登録が行われると、婚姻証明書が発行されますので、その婚姻証明書を日本語翻訳文を用意します。上記の書類を準備して、在ベトナム日本大使館にて「報告的届出」を行います。
その際に必要な書類は、下記の通りです。
・婚姻届
・ベトナム法務局から発行された婚姻証明書とその日本語翻訳文
・ベトナム人のパスポートとその日本語翻訳文
・日本人の戸籍謄本
・夫婦のパスポートの写し
上記のいずれかの方法にてベトナム人と日本人の結婚が成立したとしても、ベトナム人が日本に在留するための「日本人の配偶者等」の在留資格が出入国在留管理局で認められるかどうかは、別の問題です。
特に、日本で長く在留したいと考える外国人の方が、「日本人の配偶者等」の在留資格を欲しいがために、日本人と偽装結婚をする外国人が増加しているため、出入国在留管理局は慎重に審査を行っています。現に,入管当局は偽装結婚を含む不法滞在,不法入国の疑いのある事例については広く情報提供を呼び掛けてさえいます。
真摯な婚姻であることの証明にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
中国国籍の人との国際結婚とその手続き

「中国人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
1.中国と日本の婚姻制度の差異
日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたが、中国の婚姻可能年齢は男性22歳、女性20歳です。また、日本では離婚や死別から100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、中国では6か月間と定められています。中国人と日本人の国際結婚の手続きは、先に日本で結婚手続きを行うか、先に中国で結婚手続きを行うかによって変わってきます。
2.日本で先に結婚手続きをする場合【日本先行方式】
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
【中国人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館が発行)
・パスポート
<再婚の場合に中国人が用意する書類>
・離婚公証書または死亡公証書(※中国で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)
・婚姻届受理証明書または死亡届受理証明書(※日本で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)
上記の書類を取得して、2人で日本の市区役所等に婚姻届を提出します。
ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。
次に、中国での戸籍(居民戸口簿)を「既婚」に切り替えるため、日本の市区役所等から「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、この婚姻受理証明書を外務省と在日中国大使館で認証してもらった上で、中国人の戸籍所在地の役所に、中国語翻訳文を添付して提出します。
<中国人が短期滞在で日本にいる場合>
先に日本で結婚手続きをする場合、中国大使館からの婚姻要件具備証明書の発行は、中国人が中長期滞在の在留資格を取得している場合に可能だとされています。
90日までの在留しか認められていない短期商用や親族訪問目的の短期滞在の在留資格で来日している場合、在日中国大使館から婚姻要件具備証明書の発行がされないルールになっていますので注意が必要です。
短期滞在ビザで日本に来ていた場合は、出生公証書・国籍公証書・未婚公証書を発行してもらい、その日本語訳文を添付した上で、日本の市区役所等に婚姻届を提出します。
ただし、通常は婚姻要件具備証明書がなければ受理されません。
婚姻要件具備証明書の代わりに出生公証書・国籍公証書・未婚公証書を出したという場合、市区役所等によっては婚姻届を受理してもらえない場合がありますので、受理してもらえない場合は、先に中国で婚姻手続きを行うしかありません。
3.中国で先に結婚手続きをする場合 【中国先行方式】
まず、下記の書類を取得した上で、2人で中国人の戸籍所在地にある「婚姻登記処」にて、結婚登記手続きを行うと、「結婚証」が発行され、正式に結婚が認められます。
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(日本の法務局が発行し、外務省と在日中国大使館の認証済みのもの)
・婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
・パスポート
【中国人が用意する書類】
・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート
(※登記処によっては追加の必要書類が求められる場合もありますので、事前確認をお勧めします)
次に、日本人が3か月以内に、日本で「報告的届出」としての婚姻届の提出します。
この際、夫婦2人で行わなくても日本人の方が単独で提出することが可能です。
婚姻届の提出に必要な書類は、下記の通りです。
・婚姻届(この場合、日本人が1人で配偶者の欄も記入して問題ありません)
・中国人配偶者の出生公証書
・(中国人配偶者に離婚歴がある場合)離婚公証書
・これら公証書の日本語翻訳文
上記のいずれかの方法にて中国人と日本人の結婚が成立したとしても、中国人が日本に在留するための「日本人の配偶者等」の在留資格が出入国在留管理局で認められるかどうかは、別の問題です。
日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を欲しいがために、日本人と偽装結婚をする外国人が増加しているため、出入国在留管理局は慎重に審査を行っています。
真摯な婚姻であることの証明にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
4.婚姻後のビザの手続き
日本の手続きを先行していた場合,婚姻した後,配偶者を中国から日本へ外国人を呼び寄せる手続きを行う必要があります。
呼び寄せのためには,在留資格認定証明書の交付請求を行います。在留資格認定証明書とは,入国前に「日本でビザを取得したいのですが認められるでしょうか」という事前審査を受けたことの証明書です。この在留資格認定証明書を取得してから日本に入国することでスムーズにビザの取得ができます。
在留資格認定証明書は,日本で外国人を呼び寄せようとする人または弁護士,行政書士が取次申請人となって申請を行います。
在留資格認定証明書をもらうためには,呼び寄せようとする外国人が実際に日本でどのような活動をする予定なのかということをきちんと証明しなければなりません。書類に不備があると,たとえ真実結婚していたとしても,配偶者ビザが認められないということもあるのです。
一方,中国での手続きを先行させてから日本に来た場合,在留資格の変更手続きをしなければなりません。配偶者ビザへの変更については1~2か月程度かかることもあるため,その間に在留期限が切れてしまわないように注意する必要があります。
参考:法務省HP ビザの手続きに要する時間の統計
国際結婚とその後の外国人の呼び寄せ,在留資格の変更をご検討の方は,こちらからお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
フィリピン国籍の人との国際結婚とその手続き

「フィリピン人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
1.フィリピンと日本の婚姻制度の差異
日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたので、これはフィリピンのルールと一致します。
フィリピンは離婚が認められていませんが、それはあくまでもフィリピン人同士の結婚の場合であり、日本人とフィリピン人の国際結婚の場合は、離婚が可能です。
また日本では、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、フィリピンでは、夫との死別の場合、女性に301日間の再婚禁止期間が設けられています。
ただ、フィリピン国内で制度上、離婚が想定されていないことから、離婚の場合の再婚禁止期間はないと考えられています。
日本で先に婚姻手続きを行うか、フィリピンで先に婚姻手続きを行うかによって流れが異なりますが、日本先行方式の方が流れはシンプルです。
ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。
2.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
まず、在日フィリピン大使館で、フィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
【フィリピン人が用意する書類】
・在留カード
・出生証明書(フィリピン統計局が発行したもの)
・婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
・証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
・パスポート
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・パスポート
上記の書類を取得して、必ず2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を受領してください。
次に、日本の市区役所等に婚姻届を提出するにあたっての書類も取得します。
【フィリピン人が用意する書類】
・認証済み出生証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
・認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
参考:日本の市役所での手続き,書類https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shiminka/yokuarushitsumon/3/4/3996.html
3.フィリピンで先に結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】
まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はフィリピン統計局が発行した出生証明書を用意してください。
次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請します。
婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。
その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。
民事登記官によって正式に登録されることによって、婚姻証明書の謄本が取得できるようになりますので、在フィリピン日本大使館又は日本の市区役所等に婚姻届を提出する手続きを行います。
【日本人が用意する書類】
・婚姻届
・戸籍謄本
【フィリピン人が用意する書類】
・婚姻証明書(フィリピン統計局発行のもの)
・出生証明書(フィリピン統計局発行のもの)
・これらの日本語翻訳文
上記に従い、フィリピン人との結婚が正式に成立したとしても、当該フィリピン人に「日本人の配偶者等」の在留資格が発行されるとは限りませんのでご注意ください。
4.婚姻後のビザの手続き
婚姻した後,フィリピンから日本へ外国人を呼び寄せる手続きを行う必要があります。
呼び寄せのためには,在留資格認定証明書の交付請求を行います。在留資格認定証明書とは,入国前に「日本でビザを取得したいのですが認められるでしょうか」という事前審査を受けたことの証明書です。この在留資格認定証明書を取得してから日本に入国することでスムーズにビザの取得ができます。
在留資格認定証明書は,日本で外国人を呼び寄せようとする人または弁護士,行政書士が取次申請人となって申請を行います。
在留資格認定証明書をもらうためには,呼び寄せようとする外国人が実際に日本でどのような活動をする予定なのかということをきちんと証明しなければなりません。書類に不備があると,たとえ真実結婚していたとしても,配偶者ビザが認められないということもあるのです。
国際結婚とその後の外国人の呼び寄せをご検討の方は,こちらからお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
上陸拒否の特例について
上陸拒否とは、特定の理由により外国人が日本に入国することを拒否される法的措置です。
日本国内でオーバーステイ等により強制送還された人が再入国を希望する場合、上陸拒否の特例が適用されることがあります。
ここでは上陸拒否の特例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が法的な背景と具体的な事例を交えて解説します。
事例
(架空の事例です)
Aさんは中学から高校に入学する段階で、東京におばあさんが住んでいたことから、東京の高校に留学することにしました。
Aさんは高校受験,大学受験と勉強に励み,日本の大学へ進学します。
ある時Aさんはサークル仲間のBさんから、「この葉っぱをタバコのようにして紙に巻いて吸ってみなよ。疲れが取れるよ。」と微量の大麻草を譲り受け,「少しくらい吸ったところでどうせばれないだろう」,と思い、軽い気持ちで大麻を吸うことにしました。
Aさんが公園で大麻を吸っているときに、たまたま公園を巡回していた警察官に見つかり現行犯逮捕されてしまいました。その後Aさんは裁判所に起訴をされ、裁判では懲役8月執行猶予3年の有罪判決を受けました。
Aさんは在留資格の取消しこそなかったものの、この事件が原因となって翌年の在留更新が不交付となり、本国に強制送還となりました。
本国に帰ったAさんは、インターネット関連の事業会社を立ち上げ現在急成長をしています。
Aさんは自分が青春時代を過ごした日本でネットビジネスを手掛けたいと考えていますが、自身は大麻取締法で有罪判決を受けていることから無期限上陸拒否(出入国管理及び難民認定法第5条四項,以下法)となっており、日本でビジネスをするどころか遊びに来ることすらできません。
Aさんはこのまま2度と日本に入国することはできないのでしょうか?
法務大臣の裁決の特例としての上陸特別許可について
Aさんが再入国しようとした場合,次の規定による許可を求めることになります。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
(条文解説)
法第五条の二は、平成21年法律第79号による入管法の改正で新設されました。
この条文が規定される前は、上陸拒否に該当する者についてはたとえ人道上許可すべき事情があるような場合であっても、通常の上陸許可をすることができず、そのような者に対して上陸を許可する場合には、異議申出の手続きを経て上陸特別許可を行う必要があり、手続きが大変面倒でした。
このことについて「平成21年度入管白書」によると、「例えば、退去強制歴があるため上陸拒否期間中の外国人が、本国で日本人と会って結婚した場合に、法務大臣が、諸般の事情を考慮して上陸特別許可を与えたような場合であっても、その後、その外国人が本邦に再上陸しようとするたびに、入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可をしなければならないことになるなど、合理的といえない場合もあることから、上陸拒否に該当する特定の場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、上陸を拒否しないことができる規定を設けた」と記載されています。(入管法大全P60)。
上陸拒否の特例における具体的な申請方法としては,在留資格認定申請証明書により日本から上陸拒否となっている外国人を呼び寄せ、在留資格認定証明書での審査を通して入管側が上陸特別許可の判断を行います。
上陸特別許可のように入国審査官→特別審理官→法務大臣の三段階の手続きが省略され,手続が大幅に簡略化されています。
次に法第五条の二にある「相当と認めるとき」とは、具体的にどのような場合に「相当と認めるとき」に該当するのかについてですが、「平成25年5月10日の衆議院法務委員会において、榊原法務省入国管理局長(当時)によると「相当と認めるとき」とは、「上陸拒否事由に該当する者であっても、
その入国目的に照らし、法務大臣が上陸を求めることが相当と判断する場合には、入管法第5条の二や第二十二条に基づき上陸を認めることがあります。」と述べ、さらにその判断の基準についての質疑に対して、「個々の事案ごとに、入国目的、上陸拒否事由の内容、当該事由が発生してから経過した期間、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断することになります」とあります。
(入管法大全P63)
そこでAさんについて上記に記載された「相当と認めるとき」をあてはめてみます。
Aさんは日本で会社を立ち上げインターネットビジネスの事業を展開したいと考えているので、「経営・管理」の在留資格で在留資格認定申請証明書により在留資格申請を行います。
以下①~④の事情を総合的に考慮して、Aさんが日本で「経営・管理」の在留資格が判断されることになります。
①入国目的:すでに本国で一定の成果を上げている自身が立ち上げたインターネットビジネスの会社を日本で立ち上げたい。
②上陸拒否事由の内容:軽い気持ちで大麻を吸ってしまった。Aさんは現在、当時の過ちを深く反省している。
③当該事由が発生してから経過した期間:Aさんが強制退去で本国に帰国してから丸10年が経過した。
④その他諸般の事情:Aさんは大変優秀な起業家であり、日本にもAさんが手がけるビジネスの協力者がたくさんおり、Aさんの事業は日本でも有望視されている。
上陸拒否の特例に関する理解を深めることは、退去強制を受けたあるいは日本で有罪判決を受け上陸拒否となった外国人で、再入国を希望する人々にとって重要です。
上陸拒否の特例の適用は大変複雑であり、個々のケースによって対応が全く異なります。
上陸拒否の特例を利用して日本に再入国したい場合は、入管業務に精通している弁護士や行政書士に法的なアドバイスや支援を求めることが、
上陸拒否の特例の活用において非常に重要となるでしょう。
在留特別許可,上陸特別許可(上陸拒否の特例)についてご不安なことがある方や,強制送還された人の再入国についてお問い合わせのある方は,こちらからお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
育成就労制度とは何か?

「育成就労制度」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
2018年の入管法改定(翌19年施行)によって、深刻な労働力不足に対応するために、在留資格「特定技能」が創設されました。
ニュース報道:外国人材「育成就労」新設、技能実習を改革 閣議決定
特定技能には、最長5年間で、家族の帯同が認められていない1号と、家族帯同が可能で、通算在留期間に制限のない2号があります。
技能実習制度に替わる「育成就労制度」は、未熟練労働者として受け入れた外国人を、特定技能1号に移行できる水準に育成しようというものです。
つまり、外国人の出身国のためではなく、受入れ国である日本の労働力不足解消に資するよう、育成しようという制度です。そのため、新制度の受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」に一致させるとしています。
また、現行制度の下では、良好な技能実習2号修了者は、無試験で特定技能1号に移行できますが、新制度では、日本語と技能の試験に合格しなければ移行できません。
つまり、育成の結果、一定レベルに達しない外国人は帰国しなければいけません。特定技能1号から2号への移行にも日本語と技能の試験があります。
やはり、一定レベルに達しなければ、帰国してくださいという制度設計です。
今回の見直しの最大の争点は、転籍の自由です。「育成就労制度」では、転籍要件が緩和され、自己都合の転籍が認められるようになります。
しかしながら、同一受入れ機関での1年を超える就労、日本語と技能試験の合格などの要件が設定されることで、一定の転籍制限が維持されています。もちろんですが、たとえ要件を満たしたとしても、転籍先が見つからなければ転籍できません。
現行制度でも、やむを得ない事情がある場合には、転籍が認められていますが、監理団体や技能実習機構による転籍支援はうまく機能しておらず、外国人の権利保護という観点からすれば、転籍が実質的に保証されない限り、技能実習制度の問題点が継承されてしまう可能性が高いといえます。
これに対して、受入れ機関や地域からは、転籍要件が緩和されることで、賃金などの労働条件の良い都市部へ外国人が流出してしまうことを危惧する声があがっています。
有識者会議の最終報告書では、転籍要件の就労期間に関して、当分の間、受入れ分野によっては1年を超える期間を設定することを認めるといった受入れ機関や地域に対する「配慮」とも言える経過措置が示されています。
加えて、送出し機関、監理団体、技能実習機構などの現行の技能実習制度に係る関係諸機関が、新制度においてもすべて維持されています。
かつての日本は、受入れ国として絶対的に優位な地位にあり、多くの外国人を惹きつけることができましたが、近年では、もはや外国人にとっての移住の選択肢は日本だけではありません。
今後の日本が目指すべきは、制度によって縛らなくても、選ばれる地域をつくることだと思います。
受入れ機関や自治体、地域住民やNPOなど多様なアクターが連携・協力し、就労環境や生活環境を改善・整備し、魅力を高めるための努力をすることが必要不可欠でしょう。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
未成年者の外国人の帰化
「未成年の外国人の帰化」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
外国人が日本国籍を取得する帰化申請には、申請者が成人していることを定める「能力要件」がありますが、未成年者は帰化できないのかというと、必ずしもそうではありません。
手続き方法や、緩和条件によっては、未成年の外国人も帰化申請が可能です。
外国籍の方が日本国籍を取得する手続きのことを「帰化」といいますが、帰化をするためには様々な条件があり、その一つとして「能力要件」があります。
能力要件は、「年齢が18歳以上であり本国法によって行為能力を有している」ことと定められています。
基本的に、一人で帰化をする場合には年齢が18歳を超えている必要があるということです。
ただし場合によっては、未成年でも帰化をすることは可能です。
以下で、未成年の外国人における日本国籍取得の条件等についてご説明いたします。
帰化については法務省HPでも必要書類等について説明があります。
未成年の帰化の条件
まず、外国人が日本に帰化する条件は、一般的に以下の7つが定められています。
① 住所要件:日本に継続して5年以上住んでいること
② 能力要件:年齢が20歳以上であり、日本・国籍国の両方で成人していること
③ 素行要件:素行が善良であること
④ 生計要件:世帯単位で、十分な収入や資産があること
⑤ 重国籍防止要件:日本以外の国籍を持たない、または帰化と同時に喪失すること
⑥ 思想要件:暴力団やテロ組織に加入していないこと
⑦ 日本語能力要件:日本の小学校3、4年生レベルの日本語能力があること
このうち、未成年にとって問題になるのは、2つ目の能力要件です。
一見、未成年の外国人は日本国籍取得ができないように見えますが、この能力要件は一定の条件に当てはまると緩和されます。
また、単独ではなく、親と一緒に帰化をすれば年齢に関係なく手続きを行うことが可能です。
この場合、子供の年齢は問われず、0歳でも帰化申請が可能になります。
子供が15歳未満であれば、法定代理人である親が帰化申請の手続きを行います。
15歳以上18歳未満の未成年だと、書類の作成や面接などの帰化申請手続きは子供本人が行うことになりますが、親と一緒に帰化するなら能力要件(年齢)は問われません。
また、両親のどちらかが日本国籍である場合も、未成年でも帰化申請が可能です。
このケースは、日本人と外国人が国際結婚して生まれた子供や、すでに日本に帰化している元外国人の子供などが該当します。
この場合、「能力要件」の他に「住所要件」「生計要件」が緩和され、年齢、日本に住んでいる期間、収入を問わず帰化申請することが可能です。
さらに、日本人の養子である外国人も能力要件が緩和され、未成年でも日本国籍の取得ができます。
このケースには、日本人と結婚した外国人の子供がその日本人と養子縁組をした場合や、日本人の夫婦が海外から養子を引き取った場合などが該当します。
ただし、実子ではなく養子であると、「日本に引き続き1年以上在住している」という条件が付きます。
このケースで帰化申請をするのであれば、未成年者はそれ以前に1年以上、定住者ビザや留学ビザなどで日本に在留する必要があります。
以上のように、未成年者の外国人が帰化する場合には、様々なパターンがあり、パターンによって要件が異なりますので、「未成年者の外国人の帰化」でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。