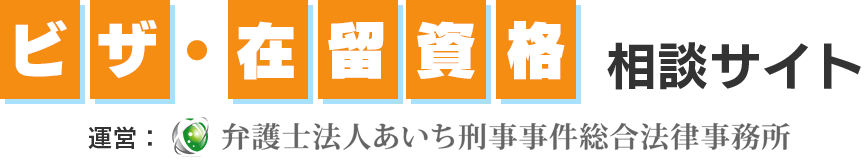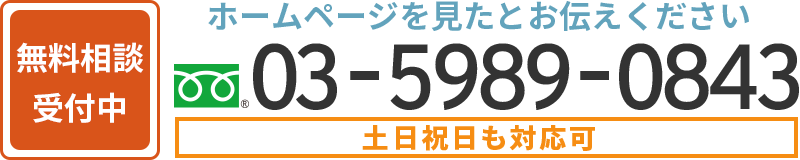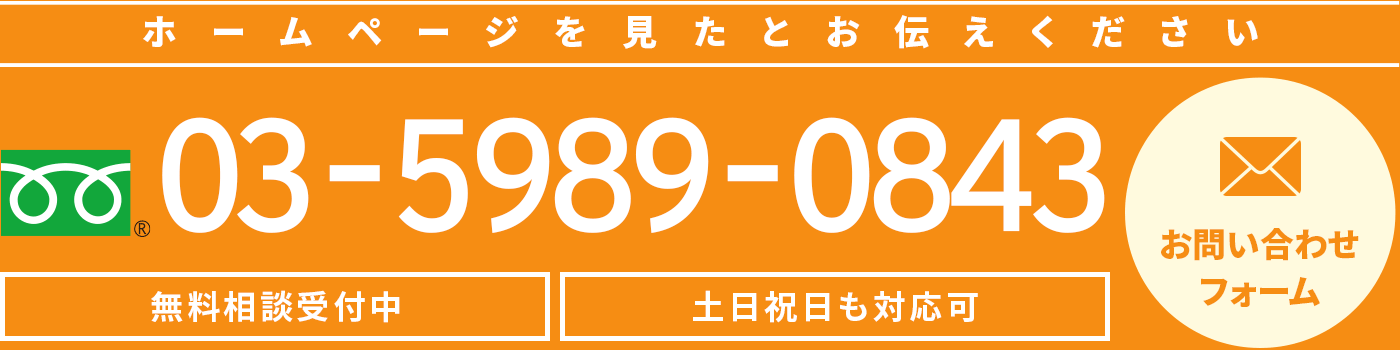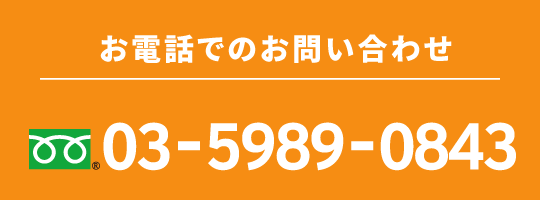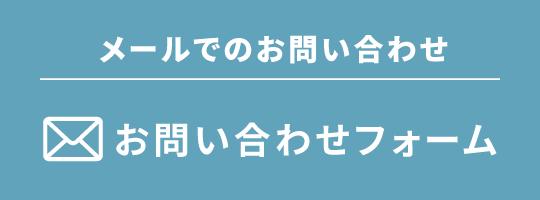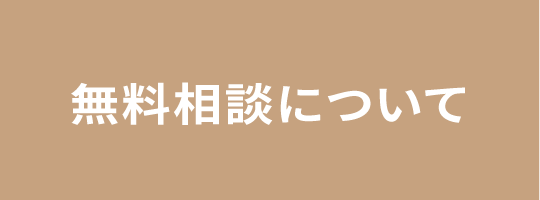Archive for the ‘在留資格・ビザ’ Category
【技術・人文知識・国際業務ビザ】職務内容説明で明暗が分かれる理由とは?行政書士が解説
技術・人文知識・国際業務ビザ|職務内容説明で明暗が分かれる理由
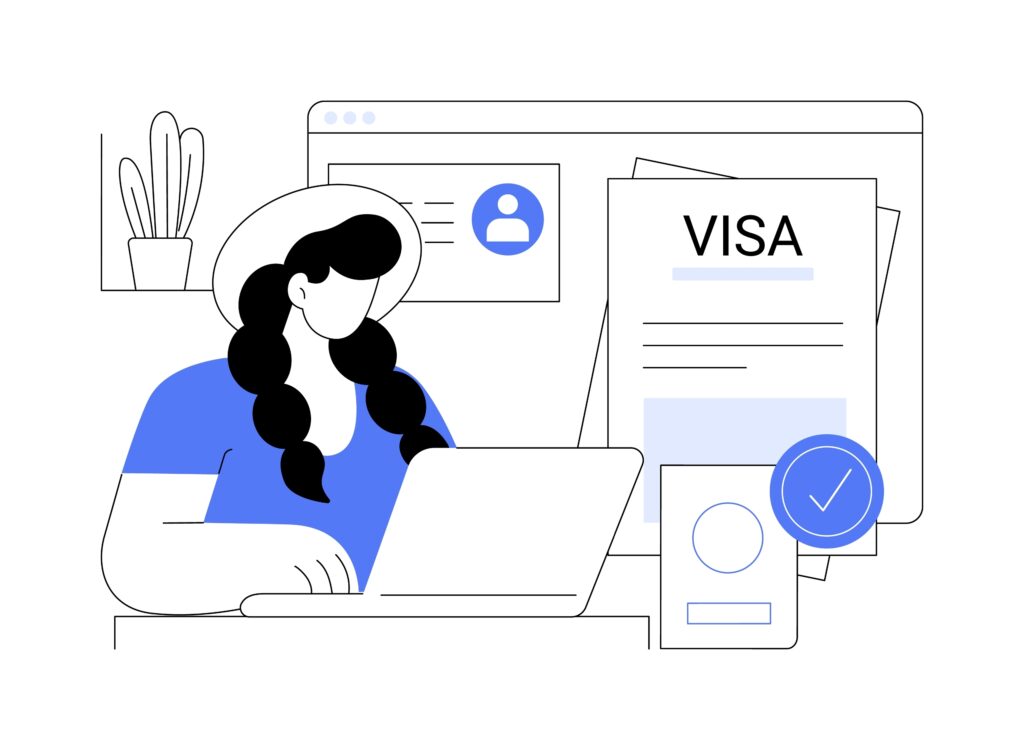
「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)は、申請者の学歴・職歴だけでなく、実際に日本で何をするのか(職務=活動内容)が審査の中心です。
同じ学歴でも、職務内容説明(職務内容説明書・業務内容説明資料)の仕方で許可/不許可が分かれます。
審査の核心は「学歴」よりも「活動との整合性」
法務省の外局である出入国在留管理庁のガイドライン(平成20年3月策定、最終改定令和6年2月)は、該当性判断を「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」と明示しています。
専門業務が“ごく一部”で、残りが専門性を要しない業務や反復訓練で行える業務だと、該当しないと判断され得ます。
一方、入社当初の研修として一時的に接客・販売等が含まれても、日本人社員にも同様に行われ、在留期間全体の大半を占めない場合は、相当性を判断した上で認め得るとされています。
申請の流れと判断ポイント
(海外から)
内定 → COE申請(国内の代理人可)→ 査証申請 → 上陸
(日本国内)
留学等 → 在留資格変更許可申請
入管が見る主な軸
①職務が「技人国」の範囲か(単純労働ではないか)
②学歴・職歴要件と職務が結びつくか(関連性)
③報酬が日本人と同等以上か
④研修があるなら合理性と期間
上記は実務上の全体像で、COEが査証発給を保証しない点も含めて公式に説明されています。
技術・人文知識・国際業務の要件を運用基準から整理
要件は大きく「活動内容(職務)」と「学歴・職歴(上陸許可基準)」に分かれます。
職務内容説明では、次の3点を“証拠で”示せるかが要です。
• 契約に基づき、継続して行う活動であること(雇用契約/委任等を含む)。
• 自然科学・人文科学の専門知識を要する業務、または外国文化に基づく思考・感受性を要する業務であること。
• 学歴・職歴要件(専攻との関連、実務経験年数)と、職務が噛み合っていること。
要件の整理表
| 観点 | ポイント | 立証資料(例) |
| 契約性・継続性 | 契約(雇用・委任・委託等)に基づき、継続が見込まれる | 雇用契約書、内定通知、組織図 |
| 活動内容(技術・人文) | 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門能力が必要 | 職務内容説明書、成果物例、ツール |
| 活動内容(国際業務) | 翻訳・通訳・語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等 | 言語・国、企画書、海外向け資料 |
| 学歴・職歴 | 専攻との関連/10年以上(関連科目専攻期間を含む扱い)/国際業務は原則3年以上(大学卒の翻訳・通訳・語学指導は例外) | 卒業・成績証明、職務経歴書 |
| 報酬 | 日本人同等額以上(実費弁償は原則含まない) | 賃金規程、同職種の給与比較 |
「単純労働」判定が出る典型パターン
ガイドラインは「未経験可、すぐに慣れます。」と書けるような業務は対象にならない旨を示し、専門業務がごく一部で、それ以外が反復訓練で習得可能な業務だと「該当しない」と整理しています。
また、ホテル分野の不許可例として「荷物運搬・客室清掃」が主たる業務のケース等が公表されています。
研修(OJT)についても、ガイドラインは「在留期間中」の判断を、1回ごとの許可で決まる在留期間ではなく、雇用契約や研修計画等から想定される就労期間全体で捉えるとしています。
その上で、雇用契約期間が3年のみで更新予定もないのに「採用から2年間研修」といった申請は認められない旨を説明し、研修が長期化する場合は研修計画等で合理性を審査するとしています。
許可されやすい/不許可になりやすい職務の境界(例)
| 区分 | 許可方向 | 不許可方向 |
| IT・エンジニア | 要件定義、設計、開発、品質管理 | 梱包、検品、ライン業務のみ |
| 企画・マーケ | 市場分析、海外向け戦略、翻訳・ローカライズ | 店頭販売、レジ、品出し、清掃中心 |
| デザイン | 主体的創作、設計、ディレクション | 補助作業のみ/接客のみ |
| 研修(OJT) | 期間限定・合理性あり・日本人も同様 | 長期化し在留期間の大半を占める |
職務内容説明書が「許可/不許可」を決める理由
基準は抽象度が高く、職名や求人票だけでは、業務が専門的かを判断できないことがあります。
研修を含む場合、入社後のキャリアステップと各段階の具体的職務内容等の資料提出を求めることがある、とガイドラインは述べています。
だから職務内容説明書は、法的評価を支える“証拠の設計図”になります。
書き方で失点しやすいポイント
| 失点パターン | 危険性 | 改善 |
| 「接客・販売など幅広く担当」 | 主業務が見えず単純労働疑い | 業務を分解し比率と成果物で示す |
| 「現場研修を1〜2年」 | 非該当活動が主となり得る | 目的・期間・研修計画を明記 |
| 「未経験可」前提 | 専門性否定に読まれる | 必要スキルを明記 |
| 専攻との接続がない | 関連性不足が直撃 | 科目→業務→成果物を線で結ぶ |
| 報酬根拠が薄い | 同等報酬で失点 | 日本人賃金根拠を添付 |
モデル記載例(短縮版)
| 目的 | 許可方向の書きぶり(モデル) | 不許可方向の書きぶり(モデル) |
| 「専門業務が主である」こと | 「海外取引先向け提案資料の作成(英語)、市場分析、契約条件交渉補助。週の業務比率:海外取引70%、翻訳・資料作成20%、社内調整10%」 | 「接客・販売等、必要に応じて幅広く対応」 |
| 「専攻との関連」 | 「大学で履修した○○(例:統計・マーケティング)を用い、KPI設計と広告効果分析を実施」 | 「大学で学んだ内容は業務に特に関係しない」 |
出典:不許可例(清掃・配膳中心、同等報酬、関連性不足等)を踏まえた留意点
公表事例と裁判例が示す「線引き」
許可例として、海外広報人材として採用後に「3か月の販売・接客研修」を経て本社の海外広報へ配属されるケースが示されています。
他方、不許可例として、ホテルで主たる業務が「荷物運搬・客室清掃」であれば不許可、採用後最初の2年間が「専ら配膳・清掃」で在留期間の大半を占めるなら不許可、などが示されています。
クールジャパン分野でも、主体的創作を伴わない補助作業のみ、接客・販売のみといったケースが不許可例として示されています。
名古屋地方裁判所平成28年2月18日判決(在留資格「技術」の事案)でも、機械製作について「設計」や「組立てを指揮」する活動は該当し得る一方、「単に機械の組立作業」は該当しない、という整理が示されています。
行政書士の業務範囲と、弁護士に依頼するメリット
行政書士は、官公署に提出する書類等の作成を業とし、提出手続の代理や書類作成に関する相談にも応じられます。
ただし行政書士法は、聴聞等での代理について弁護士法72条の「法律事件に関する法律事務」に該当するものを除く、と線引きしています。
弁護士は、訴訟事件だけでなく、審査請求等の行政不服申立事件を含む「一般の法律事務」を職務とし、弁護士でない者が報酬目的で法律事件に関する法律事務を業とすることも禁止されています。
手続支援の違い(概要)
| 争点 | 行政書士 | 弁護士 |
| 申請書類の作成・添付資料設計 | 可能(法の範囲内) | 可能 |
| 官公署への提出手続の代理 | 可能(限界あり) | 可能 |
| 不許可後の争訟対応 | 争訟代理は不可 | 申請〜争訟まで一貫 |
出典:行政書士法・弁護士法の規定。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサポート
当事務所は、職務内容を「実態」「キャリア設計」「学歴・職歴との関連」「報酬水準」の4点から再構成し、職務内容説明書を含む立証パッケージを設計します。
特に、接客・清掃・配膳など「非該当業務」が混在する案件、研修(OJT)の設計を伴う案件、専攻との関連性が説明しにくい案件では、初回の職務内容説明で“誤解の芽”を潰すことが重要です。
COEは、外務省も「査証発給を保証するものではない」と述べています。
※本文は、“””””JassoJapan”出入国在留管理庁による公開資料内のガイドライン等を主な一次資料として整理した一般情報です。
個別事情により結論は変わるため、早期に専門家へご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新で不許可を避けるには?原因と対策を解説
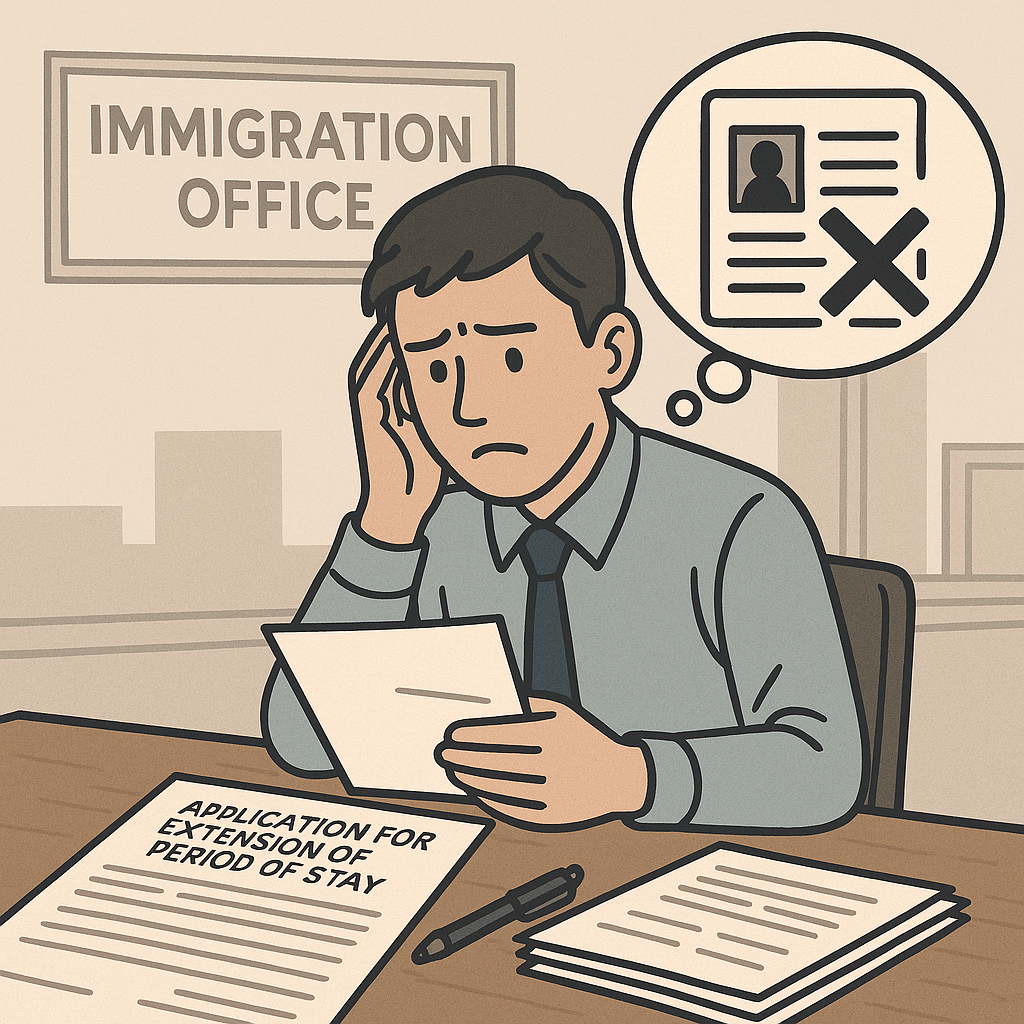
外国人の就労ビザ(在留資格)である「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新申請について、注意すべきポイントを解説します。
「延長だから簡単だろう」と思われがちですが、入国管理局の審査は初回申請と同様に厳格です。特に前回の許可後に状況の変化がある場合、更新申請が「不許可」となるケースが年々増加しています。
実際、「業務内容は問題ないと思ったのに不許可になった」「書類はすべて揃えたはずなのに結果は却下された」といった声も珍しくありません。
本記事では、具体的な不許可事例や考えられる原因を取り上げ、それぞれを法律的観点から分かりやすく解説します。
ご本人はもちろんご家族の方も、ビザ更新で失敗しないためのポイントをぜひ押さえてください。
更新申請で見られるポイント
「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新審査では、現在の活動が引き続き在留資格の要件を満たしているかが重点的にチェックされます。
入管当局は実際の職務内容や雇用状況の変化、そして法令遵守状況(納税状況や資格外活動の有無など)を細かく審査します。
特に「今後も安定して在留・就労を継続できるか」が最重要ポイントとされており、前回許可時から勤務先や仕事内容、収入状況に変化がある場合は注意が必要です。
以下では、更新不許可につながり得る具体的な原因を取り上げ、その背景にある法律上の考え方や注意点を解説していきます。
事例
〈事例:更新不許可となったAさんのケース※架空の事例です〉
インド出身のAさん(仮名)は、日本の大学で情報工学を専攻後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て都内のIT企業でシステムエンジニアとして働き始めました。
しかし1年後、Aさんは退職して別の会社に転職し、営業職として顧客対応や資料作成を主な業務とするようになりました。新しい職種は専門知識を要しない一般的な事務・営業補助の内容で、Aさんの学歴とも直接の関連がありません。
また、前の会社を退職した際に入管への所属機関変更届を提出せず、転職後しばらく無収入の期間が生じてしまいました。生活費を補うため、知人の経営する飲食店で一時的にアルバイト(資格外活動)も行っていました。
迎えたビザ更新時、Aさんの現在の職務内容は当初の在留資格の範囲から外れていると判断され、さらに転職届出の未提出やアルバイトによる資格外活動が発覚しました。
その結果、Aさんの在留期間更新申請は不許可となってしまいました。審査では、新しい職務内容が在留資格の許容範囲に合致しない点と、転職後の届出義務違反・資格外活動違反の点が決定的な不許可理由とされたのです。
(上記は仮想の事例ですが、実際にも起こり得るケースです。この後、Aさんは専門家の協力を得て不許可理由を分析し、適切な対応資料を添えて再申請することになりました。)
仕事内容の変更による在留資格とのミスマッチ
「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められるのは、専門知識を要するホワイトカラー職種の業務に限られます。
そのため、職務内容が在留資格の範囲から逸脱すると更新は認められません。例えば、本来はオフィスでの専門業務のはずが、実際には接客や倉庫作業といった単純労働に従事している場合、不適合として不許可となります。
また、転職などで職種が大きく変わった場合にも注意が必要です。新しい職務内容が以前の職務や学生時代の専攻とまったく異なる分野である場合、入管は「専門性の裏付けがない」と判断しがちです。実際、転職後の職務内容が専攻や職歴と関連性がないと不許可になる可能性は高いとされています。
法律上も、在留資格ごとに認められる活動は明確に定められており(入管法別表第一の各項目)、許可された資格と従事実態の不一致は更新拒否の理由となります。専門性と学歴・職歴の整合性を説明できない場合、更新許可は下りない可能性がありますから、特に転職をした場合等は注意が必要です。
このような事態を防ぐには、職務内容が資格の範囲内に収まっているかを常に確認し、もし範囲から逸れる場合は早めに在留資格の変更申請や専門家への相談を検討すべきです。
在留カード記載内容との不整合
在留カードの記載事項や入管に登録されている情報と、現在の実際の状況に食い違いがあると、更新審査で問題となります。
特に転職したにもかかわらず入管への届出を怠っているケースは要注意です。法律上、就労ビザで働く外国人が転職した場合は14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これを行わないと、入管のデータ上は勤務先が旧会社のままとなり、提出書類の内容と公式記録に不整合が生じてしまいます。
届出漏れは入管法違反(届出義務違反)にあたり、故意・過失を問わず審査上マイナス評価を受けます。「現勤務先を報告していない=何か不都合な事実を隠しているのでは」と疑われ、更新不許可につながる可能性が高まります。事実、転職後に変更届を出さず旧所属のままだと、不許可となった事例も報告されています。
このような不整合を防ぐには、転職や社名変更などの際には速やかに所定の届出を行うことが肝心です。また、在留カード自体の記載事項(氏名変更や国籍変更など)が変わった場合も、市区町村役場や入管での届出を忘れないようにしましょう。小さな手続き漏れが大きな不許可理由とならないよう、常に在留カード記載情報と実態を一致させておく必要があります。
勤務実績不足・雇用状況の不安定
安定した就労実績が確認できない場合も、更新不許可につながり得ます。入管は「今後も継続して就労できるか」を重視するため、過去の勤務実態が不十分だと判断されると、「この先の安定性に欠ける」と見做されてしまうのです。
具体的には、無収入のブランク期間が長かったり、勤務日数や時間が極端に少なかったりする場合が挙げられます。例えば前職を退職後、次の就職までに長期間空白があると、「実際に就労していない期間がある」と判断され不許可となったり,最悪の場合には在留資格を取り消されることになります。
また、現在の給与水準が著しく低かったり月給が日本人同等水準に遠く及ばない場合など、給与明細や出勤記録の提出がない場合も「勤務実態なし」と見なされるおそれがあります。
審査上、「活動の継続性・安定性」は在留期間更新の重要な審査ポイントです。雇用先の業績悪化などで継続雇用が困難と判断される場合も不許可の原因となり得ます。実際に、勤務先企業の連続赤字や破産開始決定が出されている等の倒産リスクが高いケースでは、「このまま在留を許可しても失業してしまう可能性が高い」として更新が認められにくくなります。
対策としては、転職や離職期間がある場合でもその理由や今後の計画を説明できるようにすること、そして直近の給与明細や雇用契約書、在職証明書などを提出して現在もしっかり働いていることを証明することが重要です。また、勤務先の安定性を補強するため、会社の決算書や事業計画書等で企業の健全性を示すことも有効でしょう。
申請書類の不備や資格外活動
提出書類の不備や虚偽記載は、どんな在留資格の審査でも致命的なマイナスポイントです。必要書類の提出漏れや書類間の記載矛盾があれば、それだけで不許可となるケースもあります。例えば、会社側が提出した複数の書類(雇用理由書や業務内容説明書など)の記載内容に食い違いがあると、入管は整合性に疑問を持ち審査でネガティブに評価します。当然ながら故意の虚偽申請(経歴詐称や偽装就労等)は発覚した時点で厳しく処分され、更新は許可されません。過去の申請で虚偽の職歴や書類を提出した経歴がある場合も、更新審査で厳しくチェックされます。さらに、住民税の未納や社会保険未加入といった法定義務の不履行も大きな減点材料です。「納税義務を果たしていない外国人」と判断されると更新が拒否されることもあります。提出書類には最新の課税証明書や納税証明書を含め、法令遵守状況もしっかり示すようにしましょう。
一方、在留資格の範囲を超えた活動(資格外活動)も重大な問題です。許可された資格で認められない仕事に就いたり、許可なく副業に手を出したりすると、入管法違反となり在留資格の取消事由や更新不許可事由に該当します。例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格で入国したのに、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど資格外の業務に従事していた場合、不法就労とみなされます。
不法就労となると、ビザの問題だけでなく刑事事件として検挙され、逮捕されるリスクまであります。
また、この在留資格は副業は禁止が原則であり、たとえ類似分野のアルバイトであっても事前に入管の許可を得ない限りリスクがあります。入管当局も資格外活動の有無については厳正に調査しており、過去に資格外活動違反があった外国人は更新審査でもその経歴が重く考慮されます。実際、留学生の資格外活動オーバーワークや、技人国ビザ保持者の無許可アルバイトが発覚して更新不許可となった事例も報告されています。
結論として、資格外活動は絶対に避けることが肝心です。副業や転職によって現在の資格で認められる範囲を超える恐れがある場合は、事前に専門家へ相談し、必要なら在留資格自体の変更申請も検討してください。法的に許された範囲内で活動する限り、更新審査でも大きな問題は生じませんが、一度でも逸脱すると信頼回復は容易ではありません。
事務所紹介
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、外国人のビザ・在留手続を熟知した専門チームがサポートする法律事務所です。
当事務所には入管業務に精通した弁護士と行政書士が在籍しており、初回のご相談から申請書類作成・入管対応まで一貫して適切な対応を提供しています。在留手続は入管法や省令・通達など複雑な基準で運用されていますが、専門家チームが正確な知識と入念な準備で臨むことで、不許可リスクの軽減に努めます。
迅速な対応も当事務所の特長です。お急ぎのケースでは可能な限り早期に相談日程を調整し、入管から通知が来た直後のご相談にも即応します。例えば、「更新申請が不許可になってしまった」「在留期限が迫っているが書類に不備が見つかった」といった場合でも、専門チームが状況をヒアリングした上で複数の選択肢から最善の対応策を迅速に提案いたします。
さらに、初回相談は無料で承っております。ビザ更新に不安を感じている方や、不許可となってお困りの方は、費用の心配なくまずは専門家にご相談いただけます。ご相談の段階から丁寧に事情を伺い、今後どのような対応策が考えられるか適切にアドバイスいたします。
当事務所では、依頼者様およびご家族の不安を少しでも和らげられるよう、密な連絡と丁寧な説明を心がけています。在留資格の更新手続きから万一不許可になってしまった場合の再申請サポートまで、豊富な経験を持つプロフェッショナルがチームで対応いたします。技術・人文知識・国際業務ビザの更新でお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用いただき、安心して日本での生活を続けられるよう万全のサポートを受けてください。
在留資格「経営・管理」とは?取得に必要な資本金・事務所要件・審査のコツを弁護士が解説
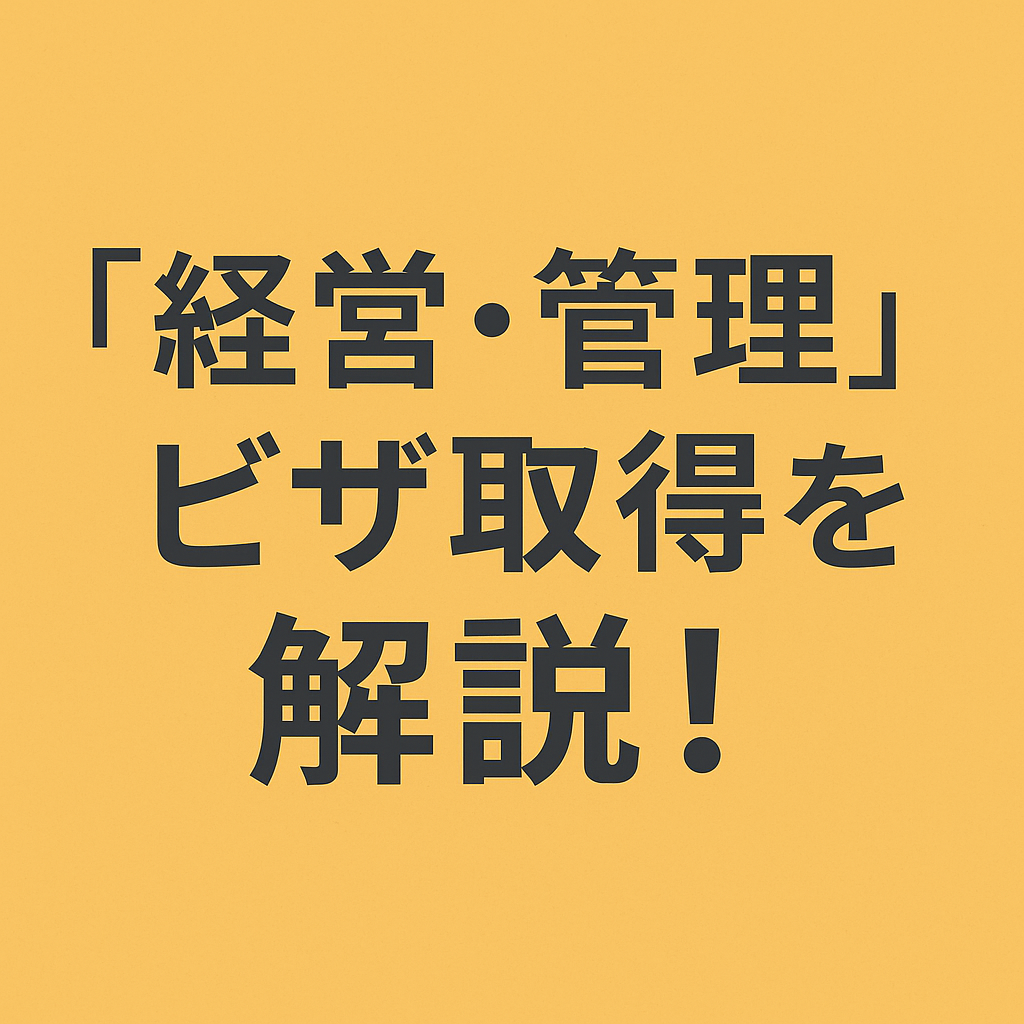
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「経営・管理」について解説します。
1.中国で大人気「経営・管理」ビザについて
近年富裕層を中心に中国国外への移住者が増加しています。2024年度の中国から国外への移住者数は過去最高でした。最近富裕層の移住先として、日本が人気になっています。
人気の理由として、地理的に日本が中国と近い、日本の教育環境が良い、治安が良い、円安で物価が低い、教育環境が良い等の点があげられています。
外国人が日本に移住するためには在留資格が必要ですが、最近中国で特に人気があるのが「経営・管理」ビザです。
2.申請人の割合
(最近7年間の「経営・管理」での新規入国者数とそのうち中国国籍者の人数と割合、2025年度は3月31日まで)
年度 新規入国者総数 うち中国 割合
~2025.3 1,792 1,242 70%
2024 4,483 2,976 66%
2023 5,295 3,745 70%
2022 4,346 2,576 59%
2021 474 269 56%
2020 1,537 864 56%
表にあるようにコロナ禍での入国拒否が解禁されて以降、経営・管理での入国が増加しており、2025年は過去最高のペースで入国しています。
新規入国のうち7割が中国となっており、特に中国からの申請者が増えています。
3.「経営・管理」ビザとは何か?
「経営・管理」ビザとは、外国人が日本に投資または人を雇用することにより事業経営を行うか又は事業の管理に従事するための在留資格です。
具体的には、会社の社長・取締役等の事業運営の意思決定者層や、事業所の支店長・工場長・部長等の管理者が該当します。
事業規模として資本金など500万円以上を投資するか又は常勤職員2名以上を雇用することが必要です。
4.なぜ中国で経営・管理の人気が高いのか?
経営・管理ビザが中国で人気の理由は、日本の在留資格の中でが比較的取得しやすい(と思われている)ことです。
「経営・管理」ビザの取得には、事業規模の要件としてとして500万以上の出資が必要ですが、米国で同様のビザ(投資駐在員ビザ)を取得するに20万~30万ドル(3000万~4500万)程度の投資が必要とされるのと比較すると、日本の場合アメリカの6分の一から8分の一の投資金額で済むことから大変リーズナブルになっています。
また「経営・管理」ビザを取得できれば、配偶者や子供を家族滞在という在留資格で呼寄せて日本の社会保険加入が可能となります。
5.経営・管理ビザの申請に重要な書類について
「経営・管理」ビザの呼び寄せでは、500万円以上の出資の他に事業計画書の提出が必須となっています。
具体的には事業内容や収支見通しをまとめた詳細な事業計画書を作成し合わせてオフイスや店舗となる物件の確保を行います。
事業計画書には今後の売上・経費計画やマーケティング戦略、組織体制などを盛り込み、事業の安定性・継続性を明らかにします。また飲食業など許認可が必要な事業は各種営業許可の取得が必要です。
6.審査のポイント
在留審査で重視されるポイントとして、事業の安定性・継続性があげられます。
事業の安定性・継続性とは、申請人のビジネスが日本で継続的に運営されて収益をあげていけるかということです。
入管の審査官は提出された事業計画書や資金計画を精査し、計画に無理がないか、十分な資金のバックアップがあるか、市場環境や集客見込みは妥当かという点をチェックします。例えば売上予測が非現実的だったり、競合調査が不十分な計画は信頼性を欠きます。
次に事業所に実態があるかが重要な審査ポイントになります。
バーチャルオフィスや月契約のレンタルスペースは不可とされており、事業所用や店舗用の事務所であることが必要です。自宅件事務所は原則NGですが、やむを得ず自宅を使う場合は戸建ての一部を明確に事業所と区切るなどの措置が必要です。
7.資金の確実性と出所
資本金500万以上を出資する場合、その資金の出所が審査されます。
申請人や出資者がどの様にしてその資金を用意したのか、銀行送金記録や預金残高証明書等で立証することが求められる場合があります。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「経営・管理」ビザについて解説しました。
「経営・管理」ビザに興味・関心のある方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
報道解説 民泊経営による経営管理ビザの取得について

「民泊経営が移住の手段に」――。大阪で中国系民泊急増、SNSに「ビザ取得は簡単」
読売新聞オンライン
こちらの報道を踏まえて,経営管理ビザについて解説します。
■日本のビザは「安すぎる」
「在留外国人統計によると、日本で暮らす中国人は2024年6月末時点で84万4187人で、過去10年間で約20万人増えている。特に経営・管理ビザで滞在する中国人は急増し、2024年 6月末時点で2万551人で、同ビザが設けられた2015年の2・8倍に増えた。
移住する中国人が増える背景には、ゼロコロナ政策への反発や経済状況の悪化に伴う将来不安がある。
中国では海外移住を意味する「潤(ルン)」という隠語も広がっている。発音表記が英語「run」と同じことから「逃げる」の意味で使われているという。
日本が人気を集める理由には、生活環境や中国からの近さがあるが、条件面もある。
海外移住コンサルティング会社「アエルワールド」(東京)の大森健史社長(50)は経営・管理ビザの要件「資本金500万円」について「格安だ」と言う。
大森氏によると、米国の同様のビザ(投資駐在員ビザ)を取得するには、20万~30万ドル(約3000万~4500万円)程度の投資が必要とされ、永住するには最低80万ドル(約1億2000万円)以上の投資が求められるという。
2022年に上海から経営・管理ビザで来日した王紅運さん(40歳代、男性、仮名)は、大阪市内にタワーマンションなど複数の不動産を持つ富裕層だ。「500万円で移住できる日本は安すぎる」と言い切った。
松村教授は「経営・管理ビザは、日本で事業を行う外国人のための在留資格だが、移住のために安易に使われているのではないか。
今後も移住する中国人が増えるとみられ、日本社会とのあつれきをうむ可能性もある。民泊を含め、事業の実態があるのかしっかりとチェックすることが必要だ」と指摘している。」
1.「経営・管理」ビザとは
外国人が日本でビジネス目的で滞在するための在留資格の一つとして「経営・管理」があります。
外国人が日本で事業活動を行う際に必要となる在留資格で2014年までは「投資・経営」と呼ばれていました。
「経営・管理」ビザの特徴として、年齢、学歴、職業経験、言語能力、婚姻状況、納税状況、資産、収入等の要件がないことがあげられます。
経営管理ビザを取得できれば、配偶者や子を家族滞在で呼寄せることができ,社会保険にも加入できます。
中国人の間では500万円以上のお金を日本に投資をすれば「割と簡単に取得できる在留資格」として人気が高く、2023年12月末の段階で、「経営・管理」ビザ全体の37,510人のうち中国籍19,334人で全体の51,5%が中国籍となっています。
近年「経営・管理」の在留資格で日本に滞在する外国人の中には、元々日本での経営活動にはあまり興味関心がなく、日本に移住する目的で「経営・管理」の在留資格を取得するケースも見受けられることが指摘されています。
2.「経営・管理」ビザの審査基準について
上記記事には経営・管理ビザを取得して「500万で移住できる日本は安すぎる」との記述がありますが、実際には500万を出資しただけでは「経営・管理」ビザを取得することはできません。
「経営・管理」の規模の要件における審査基準として第1号から第2号まであげられています。
(入管審査要領)以下解説します。
第1号
「事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。」
事業所は単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われることが必要です。
いわゆるバーチャルオフイスは認められません。独立した事業所を賃貸するか取得する必要があります。
また経営活動において人及び設備を有していて、継続的に行われている必要があります。
第2号
「申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上覧の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
第2号は外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものです。
第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の外国人職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。
この要件を満たす場合は500万以上の出資は必要ありません。
第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済み資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とするものです。
第2号ハは、イ又はロのいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準じる規模であることを要件とするものです。
基準1号、2号から見てわかる通り、500万円以上の出資の他に事務所賃貸又は購入費用、法人設立費用等が必要であり、日本の都市部で「経営・管理」ビザを取得するには少なくとも初期費用として700万円から800万円はかかると思われます。
もっとも富裕層で日本の経営・管理の取得を考えている方々から見ると500万も800万もさして違いはなく、おなじ条件の在留資格を取得するのにアメリカでは日本の3,5倍程度かかることを考えると確かに日本の「経営・管理」ビザはリーズナブルでお得な在留資格であることは否定できません。
しかしながら経営・管理の在留資格が費用面で比較的リーズナブルに取得出来ても、事業の継続が難しくなれば次回の在留更新が難しくなる場合があるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「経営・管理」ビザの手続きを取り扱って降ります。
「経営・管理」ビザについて興味・ご関心のある方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
外国人が日本で働くために必要な就労資格 その2

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が外国人が日本で働くために必要な「就労資格」について解説します。
外国人が日本で働くために必要な就労資格は、入管表別表第一の上覧の在留資格(活動資格)一の表と二の表にあげられています。
当ブログでは、入管法別表第二の表のうち「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」について、
対象職種・業種、取得条件、在留期間、その他要件・注意点について解説します。
二の表(就労資格、上陸基準の適用あり)
教育(Instructor)
主な対象職種・業種: 小学校・中学校・高等学校等の教員、専修学校・各種学校の教師、語学指導助手(ALT)など。インターナショナルスクールの教師等も含まれます。
取得条件: 原則として大学卒業以上の学歴、または教員免許状等その教育職に必要な資格を有すること。
語学(外国語)教師の場合は、教えようとする外国語により12年以上教育を受けたことが必要です。
雇用先となる教育機関からの雇用契約が必要です。
在留期間: 5年、3年、1年又は3か月
その他: 「教育」ビザは大学相当未満の教育機関での教職が対象であり、大学で教える場合は「教授」ビザとなります。
また企業経営の英会話学校等で働く場合はこの在留資格ではなく「技術・人文知識・国際業務」が適用されます。
技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)
主な対象職種・業種: いわゆる一般的なホワイトカラー職種が幅広く該当します。
例えばシステムエンジニア、プログラマー、通訳・翻訳、貿易営業、マーケティング、デザイナー、語学講師(民間語学学校)など多岐にわたります。
理工系・人文系の専門知識や国際業務スキルを活かす職種が対象です。
取得条件: 学歴要件として「業務に関連する分野の大学卒業(学士)以上又はこれと同等の教育を受けたこと。」「業務に関連する分野の専修学校の専門課程を修了したこと。」または職歴要件として「実務経験10年以上」が基本条件です。
。近年の制度緩和により、日本の専門学校を卒業し「専門士」「高度専門士」の称号を得た場合も関連業務で就労ビザ取得が可能となりました。
。職務内容と専攻分野との関連性が重視され、かつ給与水準が日本人と同等以上である必要があります。
在留期間: 最長5年(通常1年または3年での更新。更新回数に制限なし)
その他: 就労資格の中で日本で働く外国人に最も利用されている在留資格です。
製造業のライン作業や単純労働は認められず、あくまで専門知識・技能を要する職種に限られます。
専攻と職務のミスマッチがある場合は不許可となるため、採用時には職務内容の適切性に注意が必要です。
企業内転勤(Intra-company Transferee)
主な対象職種・業種: 外資系企業や多国籍企業の社員が、本社・支社間の人事異動で日本に一定期間赴任して働くケースが該当します。
。例えば海外の親会社・子会社から日本支店へ転勤してくる社員などが代表例です。
職種としては上記「技術・人文知識・国際業務」に該当するような専門的業務(技術者、管理部門スタッフ等)が中心です。
取得条件: 転勤前に海外の本店・支店等において少なくとも1年以上継続勤務していること。
日本で従事する業務が、転勤元で行っていた業務と同種であること(専門的分野の業務)も条件です。
転勤元・転勤先企業の資本関係(親子会社・支店関係)が明確である必要があります。
在留期間: 5年、3年、1年等(更新可)。
その他: 日本法人での雇用契約は不要で、在籍会社からの派遣という形になります。
同一企業内の異動であるため、学歴や職歴の要件は問われません(1年以上の勤務実績が要件となります)
介護(Nursing Care)
主な対象職種・業種: 介護福祉士として介護施設や病院等で介護業務に従事する介護士。高齢者介護施設の介護職員などが該当します。
取得条件: 日本の国家資格である介護福祉士の資格取得者であること。
通常は日本の介護福祉士養成施設を卒業し国家試験に合格するか、EPA(経済連携協定)による来日後に試験合格することで資格を得ます。
法律上日本語能力の明確な基準はありませんが、介護福祉士資格取得には専門学校入学時点でN2程度の日本語力が事実上必要であり、利用者とのコミュニケーションにも必須なため実際には日本語能力試験N2相当以上が望まれます。
在留期間: 5年、3年、1年等(更新可)
その他: 同じ介護分野でも「特定技能(介護)」やEPA介護候補者とは異なる在留資格であり、要件も大きく異なります。
(特定技能は資格不要・N4程度の日本語で可だが介護ビザは有資格者のみなど)。資格維持のため業務に就き続ける必要があり、介護職以外の仕事はできません。
興行(Entertainer)
主な対象職種・業種: 芸能やスポーツ分野で報酬を得て活動する者が対象です。
例えば俳優、歌手、ダンサー、演奏家などの芸能人やプロスポーツ選手、モデル等が該当します。
興行イベントへの出演者や、それに付随する重要なスタッフも含まれる場合があります。取得条件: 日本で行う興行(公演・興行イベント)に関する契約があることが前提です。
申請人本人に関する要件として、外国の教育機関で当該芸能活動に関する科目を2年以上専攻しているか、または外国で2年以上の実績(経験)があることのいずれかを満たす必要があります。
。また受け入れ機関(招聘元)に関する要件として、興行主に十分な経営基盤があることや報酬が適正であること等が審査されます。
在留期間: 最長3年(活動内容に応じて1年や3ヶ月など短期の許可も多く契約期間に合わせて在留期間が決定されます。)
その他: 興行ビザでは契約された興行活動以外での収入活動は認められません。興行内容によっては風俗営業法等他法令の遵守も求められます。
興行ビザには細かい区分があり(興行1号・2号など)、活動内容ごとに要件が定められています
技能(Skilled Labor)
主な対象職種・業種: 調理師(外国料理のシェフ)、ソムリエ、宝石・貴金属加工職人、衣料・織物職人、家具工芸職人、動物調教師、スポーツ指導者・トレーナー、航空機パイロットなど熟練した技能を要する職種。
日本には少ない特殊技能(例えば各国料理の調理など)に従事する外国人が対象です。
取得条件: 職種ごとに定められた相当年数の実務経験や資格が必要です。多くの場合少なくとも3~10年以上の実務経験が求められます。
例えば外国料理のコックは通常10年以上の調理実績が必要ですが、タイ料理人の場合は一定の技能証明書と直近1年の本国での調理経験があれば5年の経験でも認められる特例があります。
このように職種により要件が異なるため、事前に各技能分野の基準を確認する必要があります。
在留期間: 最長5年(更新可能。通常1年または3年ごと)
その他: 対象となる技能職種は法律で限定的に列挙されています。
技能実習を経て培った技能を実務として活かすケースもあります。技能ビザで認められる範囲外の単純労働はできません。また、日本人と同等以上の報酬が支払われる必要があります。
特定技能(Specified Skilled Worker)
主な対象職種・業種: 人手不足が深刻な産業分野における即戦力労働者を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、現在16分野(外食、介護、建設、農業、製造業など計16産業分野)で受け入れが可能です。
取得条件: 特定技能1号(中級技能者)と2号(熟練技能者)に分かれます。
1号は各分野ごとの技能試験及び日本語試験(一般に日本語能力試験N4相当)に合格することが必要です。
一方、特定技能2号は1号修了者等でさらに熟練した技能を持つ人が対象で、より高度な試験合格や実務経験が求められます。
在留期間: 1号は通算で最長5年まで(1年・6ヶ月等の在留を更新、合計5年で上限)
2号は在留期間の上限はなく、継続的に更新可能です(在留期間は最長3年までで更新回数無制限)
その他: 1号では家族の帯同は原則不可ですが、2号になると配偶者や子の帯同が認められます。
特定技能制度は技能実習で培った人材の受け皿としての側面もあり、技能実習からの移行も可能です。人手不足解消を目的とした制度のため、
待遇は日本人同等以上とすることや支援体制の整備(1号の場合、登録支援機関による支援が必要)などの条件も付されています。
技能実習(Technical Intern Training)
主な対象職種・業種: 開発途上国等の外国人が日本で技能移転を受けるための実習生制度です。海外の子会社から受け入れる企業単独型実習生や、送出機関・監理団体を通じて受け入れる団体監理型実習生が対象となります。
。職種は農業、建設、製造業など多数(91職種)168作業が指定されており、日本の企業等でOJTを通じ技能を習得します。
取得条件: 自国の送出機関などを通じ、日本の受入企業と技能実習契約を結ぶ必要があります。
入国時は技能実習1号(原則1年)から開始し、所定の試験合格など要件を満たせば2号・3号へと段階的に移行して最長5年間の実習が可能です。
各段階で技能検定の合格など一定の成果が求められます。また実習終了後は原則として習得技能を活かすため帰国することが前提ですが、優良修了者は特定技能への移行も認められています。
在留期間: 最長5年(技能実習1号=1年以内、2号=2年、3号=2年の合計)
通常は1年ごとに在留資格更新・段階変更しながら進みます。
その他: 技能実習は労働力の受入れではなくあくまで国際貢献・人材育成を目的とする制度です。
そのため転職や実習職種の変更はできず、実習計画に沿った業務のみが許可されます。近年制度見直しの動きもあり、2027年以降「育成就労」へ一本化検討されます。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、日本で働ける就労資格の中から「教育」「技術・人文・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」について、対象職種・業種、取得要件、在留期間、その他の要件・注意点について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の就労資格に関する在留申請手続きを取り扱っております。
日本で働きたい外国人の方や外国人の採用をお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
外国人が日本で働くために必要な就労資格

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が外国人が日本で働くために必要な「就労資格」について解説します。
在留資格とは何か
外国人が日本で働くためには在留資格が必要です。
日本で働くことを目的として認められた在留資格を就労資格といいます。
外国人が日本で働くために必要な就労資格は、入管法別表第一の上覧の在留資格(活動資格)のうち、一の表と二の表にあげられています。
当ブログでは、入管法別表第一の表と二の表の就労資格に掲げられている就労資格のうち「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」
「法律・会計業務」「医療」「研究」について、対象職種・業種、取得条件、在留期間、その他の要件・注意点について解説します。
一の表(就労資格)
・教授(大学教授など)
主な対象職種・業種: 大学の教授、准教授、助教など高等教育機関での教育・研究職等。
取得条件: 日本の大学や高等専門機関との雇用契約が必要です。
法律上は学歴要件は明記されていない(博士号等は必須条件ではない)ものの、通常は博士号取得者やそれに相当する研究実績があることが望ましいです。
在留期間: 5年、3年、1年又は3月
・芸術
主な対象職種・業種: 作曲家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、芸術分野の創作活動従事者。
取得条件: 特定の学歴要件はありませんが、自身の芸術作品や受賞歴など十分な実績が重視されます。
収入を伴う芸術活動であることが前提です。商業目的ではない純粋な芸術活動は「文化活動」となります。
在留期間: 5年、3年、1年又は3月
その他: 活動の継続性や収入が審査で考慮され、芸術活動以外の報酬を伴う仕事は認められません。
・宗教(Religious Activities)
主な対象職種・業種: 僧侶、司教、宣教師など宗教活動に従事する者。
例えば海外の宗教団体から派遣され日本で布教活動を行う宣教師などが該当します。
取得条件: 本国または所属先の宗教団体から派遣されていること。特定の資格や学歴要件はなく、日本で行う布教・宗教活動の内容が明確であることが求められます。
在留期間: 5年、3年、1年又は3月。
その他: 純粋な宗教上の職務に従事する必要があります。家族の帯同が可能です。
その場合、帯同する家族は在留資格「家族滞在」になります。
・報道(Journalist)
主な対象職種・業種: 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動で外国の報道機関の新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、
アナウンサーなど報道機関の職員。
取得条件: 外国の報道機関に雇用されている者、またはフリーランスで契約を結んだ上で取材・報道のために来日する者が対象です。
国営か民間かは問われません。継続的な契約が必要です。
在留期間: 5年、3年、1年または3月
その他: 報道目的以外の収益活動は認められません。
二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)
・高度専門職(Highly Skilled Professional)
主な対象職種・業種: 学術研究、専門技術、経営分野の高度人材(研究者、技術者、経営者など高度な専門能力を持つ人材)。
取得条件: ポイント制(ポイント表はこちら)による評価で70点以上を取得すること。
学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などの項目でポイントが与えられ、学歴(最大30点)、職歴(最大25点)、年収(最大50点)、年齢(最大15点)、
日本語能力(最大15点)といった評価基準があります。
ポイント合計が所定基準に達すれば認定されます。
在留期間: 原則5年(「高度専門職1号」)。
高度専門職として3年活動後は「高度専門職2号」への移行が可能です。
特に80点以上を取得した場合は最短1年で永住許可申請が可能になるなど、永住への優遇措置もあります。
・経営・管理(Business Manager)
主な対象職種・業種: 会社の経営者や役員、事業主など事業の経営・管理に携わる人。
例えば企業の社長、工場長、支店長、新規事業の起業家などが該当します。
取得条件: 日本国内に事業所(オフィス)を確保し、安定的・継続的な事業があると見込まれること。
独立した事業所の確保、事業の継続性・安定性の裏付けがあること、資本金または投資額が最低500万円以上であること、又は常勤社員が2名以上いること等の経営規模要件があります。
個人事業主として申請する場合も上記要件を満たす必要があります。
在留期間: 5年,3年、1年、4月、3月
起業準備段階では短期(4か月など)が付与され、その後事業の実態に応じて更新可能です。
・法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
主な対象職種・業種: 外国法事務弁護士及び外国公認会計士の他、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など、日本の法律に基づく国家資格を有する専門職。
取得条件: 業務独占の資格を有する者でなければ行うことができないとされている法律又は会計に関する業務を有していること。
申請の際には、その資格証明書(弁護士登録証、公認会計士証など)を提出し有資格者であることを証明する必要があります。
在留期間: 5年、3年、1年又は3か月
企業に雇用される形でも独立開業する形でも就労可能です。
・医療(Medical Services)
主な対象職種・業種:日本の免許を持つ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師など病院や診療所等の医療専門職。医師免許、看護師免許など国家資格の取得(日本の国家試験合格)が必要です。
在留期間: 5年、3年、1年又は3か月
その他: 資格取得が前提のため、来日前に日本の国家試験に合格しているか、日本の医療養成機関を卒業している必要があります。資格に基づく業務のみ許可され、それ以外の兼業は制限されます。
・研究(Researcher)
主な対象職種・業種: 政府機関や民間企業の研究員、調査員など研究活動従事者
(在留資格「教授」に該当する活動を除く)。
取得条件: 日本の公私の機関との契約に基づき研究活動を行うことが必要です。
学歴および研究経験に関する要件があり、大学卒業または同等の教育を受けた後に従事しようとする分野で修士以上の学位もしくは3年以上の研究経験を有すること、
あるいは当該分野で10年以上の研究経験があること等が求められます。
在留期間: 5年、3年、1年又は3月。
以上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、日本で働ける就労資格のなかから「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」について、対象職種・業種、取得条件、在留期間、その他の要件・注意点について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人の方の就労資格に関する在留申請手続きを取り扱っております。
日本で働きたい外国人の方や外国人の採用をお考えの経営者の方は是非ご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
在留資格「企業内転勤」について
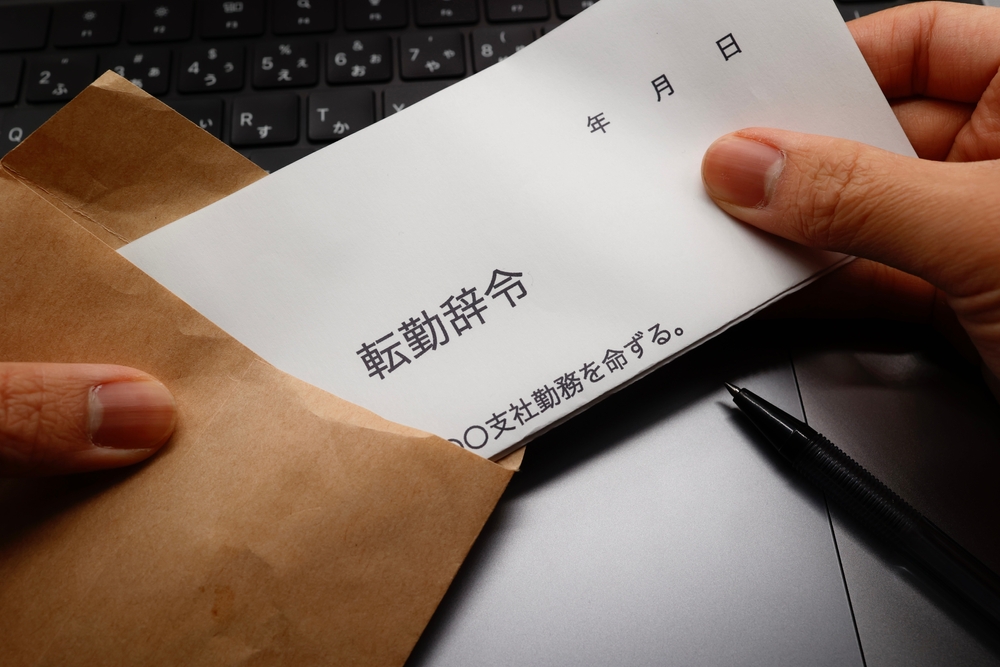
1.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
「企業内転勤」
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業 所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄 に掲げる活動。
(1)「目的」
企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられました。
同一企業等内部の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務の内部で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、
「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動を行う者が該当します。
(2)「該当範囲」
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄 に掲げる活動
(3)企業内転勤の在留資格に該当する範囲は以下の①、②です。
①「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動ですが、
同一企業内の転勤者として本邦において限られた期間勤務するものである点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。
②「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち
少なくともいづれかを必要とする業務に従事する活動です。
(4)「留意事項」
① 同一の法人内で異動をして「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はありません。
② 本邦にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません
③ 本邦にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものである必要があります。
企業内転勤のビザについて,必要となる申請書類等はこちら(法務省 出入国在留管理局HP)
2.上陸許可基準
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄 に掲げる活動で申請人が次のいずれにも該当していること。
第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表 の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,
その期間(企業内転 勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に 従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること
第2号
「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。」
「上陸許可基準の内容」
(ア)「技術・人文・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後本邦において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ありません。
(イ)申請人が本邦の本店、支店、その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して本邦にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。
「申請に係わる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において・・・
継続して1年以上あること」とは、新たに採用した職員を直ちに本邦に転勤させることは認めないということです。
これは外国企業が本邦における労働力を確保しようという目的だけのために、その企業において何ら在留資格「技術・人文・国際業務」に該当する業務を行ったことがない
新規採用職員を本邦に転勤させることを防止する趣旨です。
「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。」とは、安価な労働力防止による国内労働市場の確保のため、低賃金での業務を認めないという趣旨です。
また同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬以上であることが必要です。
「立証資料」として
所属機関となる本邦の公私の機関は、カテゴリー1から4に分類され、所属機関がいずれのカテゴリーに属するかに応じて各種申請の際に提出を要する立証資料に差が設けられています。カテゴリー1から4までのうち、1が立証資料の免除が大きく、2,3と少なくなり、1から3までのいずれかのカテゴリーに該当することの立証がなければカテゴリー4に該当するものとして免除は受けられず、入管側が求める全ての立証資料の提出が必要となります。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「企業内転勤」について解説しました。
海外の事業所から日本国内にある事業所に社員を転勤させたいが在留申請手続きについて不安のある方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
在留期間中に刑事・行政処分を受けた場合、その後の在留手続きはどうなるのか?

日本に在留している間に刑事処分・行政処分を受けてしまうとビザが取り消されてしまうのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.刑事処分によってビザが取り消されてしまうケース
在留期間中に刑事事件をおこして無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられたケース(執行猶予の言渡しを受けた者を除く)
本ケースでは、例え在留期間中であったとしても、判決確定後は刑務所に移送され服役することになります。服役中に入管審査官が退去強制手続きを進めることがあります。
刑期満了又は仮釈放後は日本人のように刑務所から外に出られるわけではなく、刑務所から出入国在留管理署(以下入管)内にある入管収容施設に直接移送されて収容されます。
出入国管理及び難民認定法、以下法)別表一(日本での活動に基づく在留資格)と法別表二(身分又は地位に基づく在留資格)の区別なく適用されます。
入管収容施設に収容されてからは、退去強制事由に該当しないと判断されない限り、原則30日以内に被収容者(入管に収容された外国人、以下被収容者)に対して退去強制処分が決定されます。
被収容者が入管施設に収容されている場合に被収容者の収容を解く手続きとして仮放免と監理措置があります。
仮放免とは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度です(法第54条)。
監理措置は令和5年の出入国管理法改正で新たに設けられました。
監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。
なお、監理措置は、退去強制令書発付前のもの(法第44条の2以下に規定)と、退去強制令書発付後のもの(法第52条の2以下に規定)とがあります。
健康上、人道上の理由以外の理由で収容の一時的解除を求める場合は監理措置によることになります。入管収容施設に収容された外国人が今後も日本に長期滞在したい場合は、退去強制処分が発付される前に在留特別許可を申請して新たに在留許可が認められる必要があります。
2.特定の犯罪で有罪判決を受けた場合
有罪の判決を受けた場合に法別表第一、法別表第二の在留資格に共通して適用されるケース
本ケースに該当する退去強制該当事由として、他人名義のパスポートによる不法入国、不法就労のあっせん、在留カードの偽造又は所持、在留カードの偽造、不法就労、在留期間超過、人身取引、旅券法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、覚醒剤取締法違反等で有罪判決を受けた場合、売春又は売春のあっせん、勧誘等があります。
出入国管理行政の根幹を揺るがしかねない行為や犯罪、社会的利益を著しく侵害する危険性のある犯罪等を法第24条で限定して列挙しています。
3.特定の刑法犯で執行猶予以上の有罪となった場合
法第24条で定める退去強制事由で、法別表第一の在留資格に該当するケース
法別表第一に記載されている在留資格の外国人は、以下の罪による場合は1年以下の懲役若しくは禁錮又は執行猶予付きの判決に処せられたときでも退去強制該当事由になります。
住居侵入罪、通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造、支払い用カード電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕および監禁の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪、窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条の二若しくは第一条ノ三の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開鍵用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
参考:外国人が逮捕されてしまった場合
4.その他の刑法犯で1年以下の実刑判決を受けた場合
法24条列挙事由以外の罪で1年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金に処せられたケース
原則として在留期間中に退去強制手続きは始まらず、次の在留期間まで在留資格は継続します。在留更新時に,刑事処分を踏まえて在留状況を審査されます。
在留更新時の審査で「素行に問題がある」と判断されると,在留更新が認められない場合があります。在留申請更新時に反省文や嘆願書等を提出して在留更新許可が認められるように対策が必要です。
5.その他の刑法犯で執行猶予判決を受けた場合
法24条列挙事由以外の罪で1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられたが執行猶予の言渡しを受けたケース
4と同様の扱いとなりますが、本ケースでは刑事処分後の在留更新は「素行に問題あり」として在留更新が認められることはかなり厳しくなります。
法別表一の在留資格の場合はもとより法別表二による在留資格の場合でも、在留資格更新時に滞在中に「素行に問題あり」として在留更新が不許可となる場合があります。
なお本ケースの場合、上陸拒否の特例を受けない限り、いったん日本から出国すると無期限で日本に入国できないので注意が必要です。
6.行政処分を受けた場合
在留更新中に速度超過や駐停車違反で行政処分を受けたケース
速度超過や駐停車違反により行政処分を受けた場合、それだけで退去強制手続きに進むことはほぼありませんが、次の更新申請の時に「素行に問題あり」と判断され在留期間が短縮されることがあり得ます。在留更新時に反省文や理由書等を提出するとよいでしょう。
以上1から6までのケースに分けて刑事処分・行政処分を受けた後の在留手続きについて解説しました。
上記のケースから分かるように在留期間中に刑事処分を受けるとその後の在留更新手続きは極めて困難となります。
また行政処分のみの場合でも在留期間が従来の5年や3年の在留期間から1年の在留期間に短縮されたりすることもあります。
在留期間中に刑事・行政処分を受けてしまい在留更新手続きでお悩みの方は、お一人で悩まずに是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
「再入国許可と上陸拒否の特例」について

(架空の事例)
永住者のAさんは現在外資系企業の日本支店で働いています。
Aさんは3年前に窃盗事件をおこし懲役1年、執行猶予3年の罪に処せられました。
判決後は幸い勤務先からの懲戒解雇は免れました。Aさんは事件後心機一転し仕事を頑張った結果、先日海外にある本社の管理職として異動の内示がでました。
Aさんは妻と子供を日本に残し単身で海外に赴任することを考えていますが、自分が以前おこした事件の影響で、日本出国後再び日本に再入国できるのかについてとても心配しています。
日本で有罪判決に処せられたAさんは、海外勤務修了後再び日本に戻ってくることは出来るでしょうか?
1.再入国許可
Q 再入国許可申請とは何ですか?
A 在留資格を取得した外国人は、当該在留資格に基づいて日本に滞在する法的資格がありますが、この資格は当該外国人が日本から出国することにより失われます。
そこで日本に在留する外国人が日本を出国後もこの法的資格を維持するための許可を受ける必要があります。この許可申請手続きを再入国許可申請といいます。
再入国許可を受けた場合は、従前の在留資格がそのまま維持されるので、日本出国後、再度日本に入国する際に改めて在留資格申請手続きをする必要がありません。
再入国の有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。再入国許可を受けて出国している外国人は、その有効期間内に再入国することができない事情がある場合には、有効期間の延長を申請することができます。この場合の延長をすることができる期間は1年をこえず、かつ、当初の再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲内です。
この有効期間の延長の許可は旅券又は再入国許可許可書にその旨を記載することによって行われ、その事務は、在外に日本国領事館等の委任するものとされています。
2.前科があっても再入国許可申請ができるのか
Aさんが海外勤務後日本に戻るためには、日本の在留資格を失わないために管轄の入管で再入国許可申請を行い再入国許可を受ける必要があります。
再入国許可申請にあたり、Aさんは3年前に窃盗事件をおこし懲役1年以上の有罪判決に処せられていますが、この場合Aさんの再入国はどうなるのでしょうか?
出入国管理及び難民認定法(以下法)第5条では日本への上陸拒否にあたる場合を例示しており、法5条1項4号では無期限上陸拒否にあたる場合として、
「日本国又は日本国以外の国に法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。」
と規定しています。
「1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられた」場合に執行猶予も含むとして運用されています。
Aさんには法5条1項4号が適用され、日本から出国すると日本への入国を拒否されAさんは海外転勤をすると永久に日本に戻ってこれないことになりますが、法5条1項4号には例外がないのでしょうか?
再入国許可が認められる場合もある
法5条1項4号に該当する場合、原則として永久に日本に入国することは禁止されますが、事情によりどうしても日本を出国して海外に行かなければならない場合もあります。
法5条1項4号に該当する場合は全て一律に上陸拒否とすることは人道的に問題生じるおそれがあります。そこで法5条の2では上陸拒否の特例を規定し、無期限上陸拒否の例外について規定しています。
法5条の2「当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないこととすることができる。」
法5条の2が適用される典型的な事例として、「上陸特別拒否事由に該当することになる特定の事由と同じ事由に基づく退去強制手続きにおいて在留特別許可を受けた者に対して、再入国許可を行った場合」があります。
Aさんは再入国手続き申請の際に、自分が出国後に日本への再入国が必要であることについて法務大臣に相当の理由を示して、上陸拒否の特例を受けることができればAさんは海外転勤ができます。
3.通知書について
Aさんに上陸拒否の特例が認められると、「法5条1項4号のみを理由として上陸を拒否しない」との趣旨を記した通知書が発行されます。
入管法施行規則第4条の2第2項「特定の事由のみによっては上陸を拒否しないこととしたときは、その外国人に通知書を交付するものとする」
通知書には以下の記載があります。
氏名
生年月日
国籍・地域
住居地
期限
事由(法5条〇項〇号に規定された上陸拒否の対象となる事由)
この通知書を、入国の際に携行(通常はパスポートに添付)して、入国審査官に提示することで日本への入国が可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では上陸特別許可申請について取り扱っています。
日本への上陸許可についてお悩みの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
日本人の実子をもつ外国人親の在留資格
「日本人の実子をもつ外国人親の在留資格」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

1.事例
日本に滞在する外国人女性Aさんは、日本滞在中に内縁関係にある日本人男性との間に子どもをもうけました。子どもは日本人男性の認知を受けて現在Aさんが日本で育てています。
Aさんがこの先日本で仕事をして子どもを育てていくためにはどのような在留手続きが必要となるでしょうか?
2.どのようなビザが取れるのか
上記のケースについて,「日本人の実子をもつ外国人親が日本に滞在するのに必要な在留資格の扱いについて」という法務省からの通達が出ています。
平成8年7月30日通達(法務省入国管理局長通達第2565号「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱について」
「表記(引用者注:日本人の実子を扶養する外国人親の取扱い)については、地方入国管理局長が諸般の事情を考慮して「定住者」と認めることが相当と判断した場合には本省に通達し、本省で個々に拒否の判断を行い、許可されたときに限り当該外国人親の在留を認めてきたところですが、日本人の実子としての身分関係を有する未成年者が我が国で安定した生活を営めるようにするために、その扶養者たる親の在留資格についても、なお一層の配慮が必要と考えられます。ついては、扶養者たる外国人親から在留資格の変更申請があったときは、下記のとおり取り扱うこととされたく、通達します」
と記載され記書きとして「未成年かつ未婚の実子(注1)を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を監護養育していることが確認できれば、地方入国管理局(支局を含む。以下同じ。)限りで「定住者」(1年)への在留資格の変更を許可して差し支えない。」と規定しています。
注1「日本人の実子とは、嫡出・非嫡出子を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わない。日本国籍を有しない有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要」
通達の趣旨は「日本人と外国人との間の婚外子出生子が増加していることを踏まえこれら日本人の実子が外国人親とともに本邦で生活を営めるようにするため、未成年かつ未婚の日本人の実子が監護養育する外国人親について、法務大臣が特別な理由を考慮し「定住者」の在留資格により在留資格を認めることとした」ものです。
定住資格とは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に付与される在留資格です。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動(定住者告示)と定住者告示に定めがないもの(告示外定住)の2種類があります。
本ケースで取り上げている「日本人の実子をもつ外国人親に定住資格を認める場合」は定住者告示に定めがないもので「告示外定住」と呼ばれるものです。
3.具体的な手続きは?
日本人の実子をもつ外国人親が、入管法別表第1の在留資格で在留している場合、今後も子と日本で暮らすことを考えているケースではどの様な手続きをすべきでしょうか?
現在の在留資格から定住資格に在留資格変更手続きをすることができます。
「定住者資格」は就労制限がなく、身分による在留資格なので就労による在留資格よりも安定的・継続的に日本に滞在することが可能となります。
「定住者資格」で継続して5年日本に滞在することで、永住申請の要件の一つである国益要件を充足することができます。
定住者の在留資格に関する手続き,書式についてはこちらから。
4.オーバーステイにより在留資格がないケースでは、どの様な手続きが必要ですか?
オーバーステイの状態では,そもそもの在留資格が無いので、このままでは強制送還となります。
日本で生活していくためには退去強制処分が発令される前に在留特別許可申請をして
法務大臣に自分が在留を許可すべき特別な事情があること示して定住者資格を認めてもらう必要があります。
法務省では在留特別許可をするかどうかの判断において、審査の透明性を図る目的で在留特別許可のガイドラインを作成しています。
ガイドラインによれば、在留特別許可認める方向での積極的要素として「家族とともに生活する子の利益の保護の必要性」をあげています。
在留特別許可の判断において在留許可を認める方向で特に考慮する積極的要素として
①子が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子であること
②外国人親が子を扶養していること
③子が未成年かつ未婚であること
④外国人親が子と相当期間同居し、子を監護及び養育していること
①~④全ての事情を満たす場合には、法務大臣が在留を許可すべき特別な事情を判断するうえで、在留特別許可を認める方向で特に考慮する積極的要素となります。
5.「定住者」への在留資格変更申請手続き・在留特別許可申請手続きに関して必要となる資料はどのようなものがありますか?
子の戸籍謄本、住民票、子の在園証明書、在学証明書、子の扶養者の在職証明書、
外国人親の在職証明書、納税課税証明書、本邦に居住する身元保証人の身元保証書等
があります。これらの資料を元に「定住者」への在留資格変更申請手続き・在留特別許可申請手続きを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日本人の実子を監護・養育する外国人親の在留申請手続きを扱っています。
日本人の実子を監護・養育するために必要な在留申請手続きでお悩みの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。