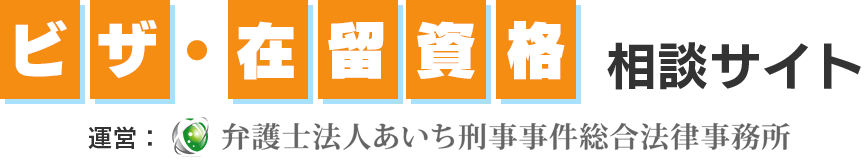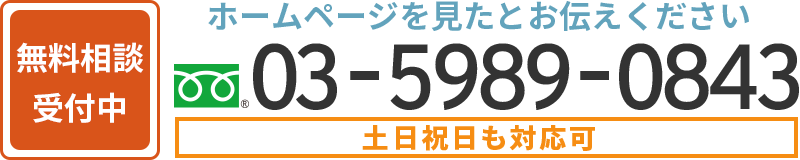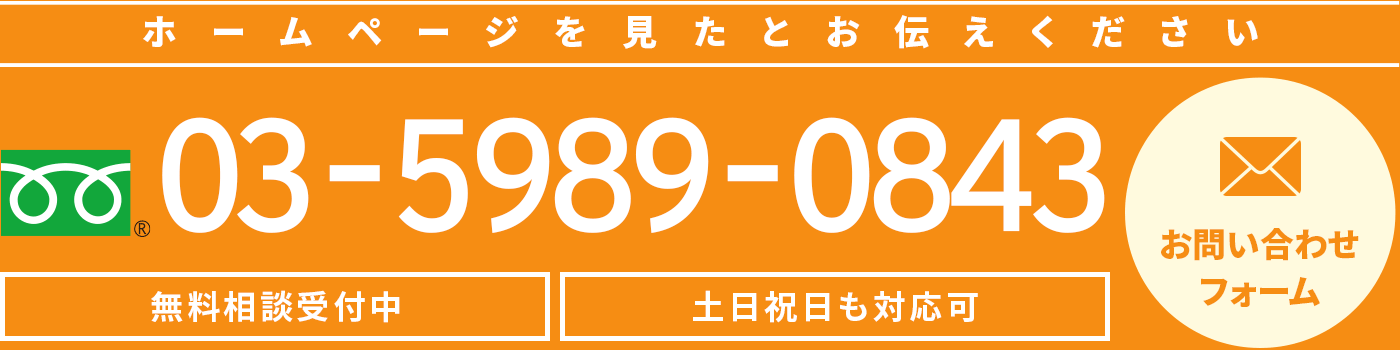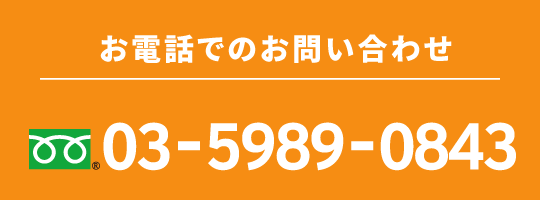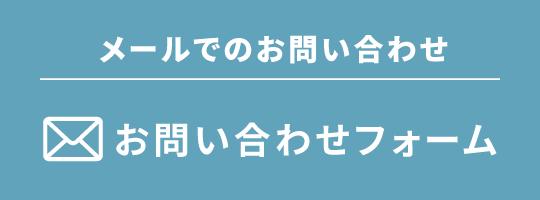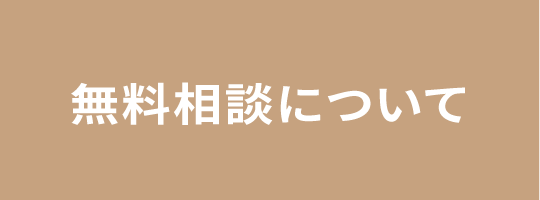このページの目次
外国人雇用の法的リスクと注意点
日本で働く外国人労働者は増加の一途をたどり、2023年10月時点で約205万人(全雇用者の3.4%)に達しています。しかし、中小企業や派遣業者の中には法的リスクへの認識が浅いケースも見られます。本稿では、外国人雇用に関する主要な法的リスクと注意点を平易な日本語で解説し、特に法的リスクを意識していない層に警鐘を鳴らします。 実際のトラブル事例や制度上の留意点、陥りやすい誤解、そして行政指導・罰則の例も紹介します。
代表的な法的リスク
- 入管法違反(不法就労): 適切な在留資格(ビザ)を持たない外国人を働かせたり、在留資格で認められていない職務に就かせたりすると「不法就労助長」に該当します。近年この取り締まりは厳しくなっており、実際に多くの派遣会社経営者が不法就労助長罪(入管法違反)の疑いで逮捕・送検されています。不法就労助長罪に問われた場合、外国人本人だけでなく雇用主も処罰対象となり、労働者派遣事業の許可取消しといった事業継続上のリスクもあります。法定刑は現行で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですが、2025年6月からは「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に厳罰化されています。
- 労働基準法違反: 外国人労働者であっても労働基準法や最低賃金法など労働関係法令は日本人と同様に適用されます。賃金の未払い、最低賃金を下回る給与、長時間残業や休憩未取得、安全配慮義務違反などがあれば違法です。例えば、厚生労働省が外国人技能実習生の受入企業を調査したところ、約7割に当たる事業場で違法な残業や低賃金など労基法違反が確認され,監督機関は違反企業に是正指導を行い、重大・悪質な場合は書類送検など厳正に対処しています。
外国人だからといって違法な労働条件が許されることは決してなく、企業経営者や担当者も処罰対象となり得る点に注意が必要です。
- 社会保険未加入: 外国人であっても所定の条件を満たす労働者は健康保険・厚生年金保険、雇用保険などの社会保険に加入させる義務があります。「外国人だから社会保険はいらない」という誤解がありますが、国籍に関係なく違法行為となるので注意してください。企業が従業員を社会保険に加入させないままでいると、健康保険法・厚生年金保険法により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される恐れがあります。また未加入だった分について最大2年遡って保険料を納付する義務が発生し、企業・従業員双方に追加負担が発生します。
- 在留資格の不適切運用: 在留資格ごとに認められた範囲を超える就労は資格外活動となり違法です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの人に工場ライン作業や飲食店の調理・接客など単純労働をさせることはできません。留学生や家族滞在の在留資格で週28時間を超えてアルバイトをさせるのも資格外活動に当たります。また制度上、技能実習生を他社に派遣労働させることは禁止されており、特定技能も原則として受入企業との直接雇用が求められます(農業・漁業分野を除き派遣形態は不可)参考:政府HP。このように在留資格ごとの制約を無視した運用は入管法違反につながります。
実際に起きたトラブル事例
法令違反によりトラブルに発展した実例をいくつか紹介します。どの業種でも起こり得る問題であり、他人事ではありません。
- 飲食業の事例:ある飲食チェーンでは、外国人社員にビザで認められていない調理業務を担当させていました。その結果、入管難民法違反(資格外活動による不法就労助長)で社長と社員数名が逮捕され、法人も書類送検される事態となりました。摘発時、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が厨房で調理をしており、同ビザでは飲食店の調理やホール接客は認められないにもかかわらず働かせていたことが問題視されました。
- 派遣業の事例:人材派遣会社が在留資格のない不法残留の外国人を派遣社員として登録し、製造業の工場へ違法に派遣していたケースがあります。その派遣会社の社長は出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕されました。調査の結果、その会社には約600人もの派遣労働者が登録されており、その半数近くが外国人でした。人手不足を背景に、不法滞在と知りつつ働かせていた悪質な例であり、派遣会社ぐるみで違法就労を助長していた実態が明らかになっています。
- 建設業の事例:建設現場でも違法就労の摘発例があります。金沢地裁では、不法滞在のベトナム人を工事現場で働かせた会社役員に対し、懲役3年・執行猶予5年および罰金50万円の有罪判決が言い渡されました。わずかな人件費削減のために不法就労を手助けした結果、刑事処分を受けた形です。このケースでは違法就労で得た利益の没収も命じられており、違反が発覚した場合のダメージの大きさが窺えます。
外国人雇用にあたっての制度上の留意点
外国人を雇用する際には、以下のような制度上のポイントを押さえておく必要があります。
- 在留資格ごとの就労範囲を把握する: 外国人が保有する在留資格が、その人に従事させる予定の業務内容に合致しているか確認することが最重要です。就労制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)の場合は職種制限なく働けますが、それ以外の就労ビザでは認められた職種・業務のみ就労可能です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは通訳や設計など専門職はできますが、工場のライン作業や飲食店のホール業務などは該当せず許可されません。採用前に在留カードで資格種別と在留期限を確認し、職務内容との適合性を慎重に見極めましょう。
- 資格外活動許可と週28時間ルール: 留学生(在留資格「留学」)や家族滞在など、本来就労が認められていない在留資格の外国人でも、「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし週28時間という時間制限は全勤務先の合計であり、残業も含めて28時間以内に収める必要があります。
例えば2つの事業所で掛け持ちする場合、両方の労働時間を足して週28時間までです。また学業が本分の留学生等に深夜残業や長時間労働をさせることは認められていません。28時間を超えて働かせると企業・本人双方に罰則が及ぶ可能性があるため、シフト設定時には十分配慮してください。 - 技能実習・特定技能制度の理解: 技能実習生は人材育成を目的とした制度であり、「労働力の需給調整の手段」として利用することは禁止されています。
したがって技能実習生を派遣社員のように他社で働かせることはできません。実習計画で定められた受入企業・職種以外で就労させると、技能実習法違反となり実習計画の取消しや受入れ停止処分につながります。一方、特定技能外国人は人手不足分野の即戦力として受入れが認められた在留資格ですが、受入企業との直接雇用が原則ですmhlw.go.jp。特定技能について派遣形態が例外的に許可されるのは農業・漁業の分野に限られておりmhlw.go.jp、それ以外の業種で派遣会社が特定技能の人材を他社に送ることはできません。これら制度の運用ルールを誤解すると違法行為となるため注意しましょう。 - 雇用状況の届出義務: 外国人を雇用した場合、事業主はその外国人の氏名や在留資格などをハローワーク(公共職業安定所)へ届け出る法的義務があります(雇用対策法第28条)。採用時だけでなく離職した場合にも届出が必要です。この「外国人雇用状況届出」を怠ったり虚偽申告したりすると、30万円以下の罰金対象となり得ます。うっかり提出を忘れている企業もありますが、行政からの指導やペナルティのリスクがあるため必ず期限内に届け出を行ってください。
無自覚な派遣業者が陥りやすい落とし穴
外国人雇用の現場では、悪意はなくとも誤解や思い込みから法令違反に陥るケースがあります。派遣業者や中小企業が特に注意すべき落とし穴や勘違いを整理します。
- 在留カード確認の不十分: 「有効な在留資格を持っているはず」と思い込み、在留カードの真偽や在留期限、就労制限内容をきちんと確認しないまま雇用契約を結んでしまうケースです。例えば派遣元が在留資格のチェックを怠り、派遣先で資格外の業務に就かせてしまうと、外国人本人だけでなく派遣元・派遣先も不法就労助長罪に問われる可能性があります。実際に本人が偽造在留カードを所持していて見抜けず違法就労させてしまった例もあります。雇用時には必ず在留カードの表裏をコピーして確認し、必要に応じて入管庁のサイトでカード番号の真偽照合を行うなど万全を期しましょう。
- 「ビザがあれば何でもできる」という誤解: 在留資格の内容まで考えず、「とにかく就労ビザを持っているから大丈夫だろう」と安易に受け入れてしまうミスです。重要なのはビザの種類ごとに許可された活動範囲であり(法律上“就労ビザ”という名前のビザは存在しません)、そこから外れる仕事は例え本人が希望しても違法になります。例えば留学生や家族滞在の人をフルタイムで働かせたり、技能ビザの料理人に別業種の作業をさせたりしてはいけません。前述の飲食店の例では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者に調理業務をさせていたことが逮捕につながりました。このようにビザの内容と現実の業務が合致しているか、常に照らし合わせる意識が必要です。
- 社会保険手続き漏れ: 前述のとおり、外国人であっても一定の勤務形態であれば社会保険への加入が法律上の義務です。しかし一部の事業者には「短期滞在だし年金はかわいそう」「手取り減るから加入させない方が本人のため」といった誤った善意や慣行で未加入のまま働かせているケースがあります。国籍は関係なく社会保険加入は義務であり、加入させないこと自体が法令違反です。後から監督機関に発覚すれば会社として処罰・追徴を受けるだけでなく、従業員本人にも過去分の保険料負担が生じて迷惑をかけてしまいます。外国人にも制度の趣旨を丁寧に説明し、必ず加入手続きを取りましょう。
- 留学生アルバイトの時間超過: 深刻な人手不足から、つい留学生アルバイトに週28時間を超えてシフトに入ってもらうケースがあります。しかし28時間制限は厳守事項であり、1分でも超過すれば資格外活動となってしまいます。中には「複数店舗で28時間ずつ働けば大丈夫」と誤解する例もありますが、28時間は全職場合計です。もし留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は特に慎重に全体の労働時間を把握する必要があります。万一オーバーすれば、学生本人も処分を受け日本での将来を絶たれかねませんし、受け入れ企業側も罰則の対象となります。繁忙期でも28時間以内に抑える工夫(シフトの調整や日本人スタッフとの分担など)を徹底してください。
- 実質的な違法派遣: 派遣業の許可を持たないのに業務委託などの名目で実質的に労働者を他社へ送り出す行為も落とし穴です。特に外国人労働者を別会社で働かせる際、形式上は請負契約にしていても実態が指揮命令を受ける労働者派遣なら労働者派遣法違反となります。先述の事例では、派遣許可の無い会社がSNSで集めた在留不明のベトナム人を各地の職場に派遣し、結果的に社長が逮捕されています。派遣業は許可制であり、特に建設現場や警備業務など派遣自体が禁止されている業種もあります。無自覚に法律違反のスキームに手を染めないよう、疑わしい場合は専門家に相談しましょう。
行政指導や罰則の具体例
最後に、外国人雇用に関して違反が発覚した場合に科される行政指導や処罰の例を整理します。違反内容によって行政上の措置と刑事上の罰則の両面から制裁が科される可能性があります。
- 入管法違反に対する罰則: 不法就労助長罪に対しては、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます。悪質な場合は懲役刑と罰金刑の両方が科されることもあり、法人が違反した場合は両罰規定により法人自体にもより重い罰金刑が科され得ます。実際に京都では、不法就労あっせんを行ったコンサル会社役員らが逮捕され、企業名が報道で公表され社会的信用を失墜する結果となっています。さらに一度摘発されると、既存の外国人受入れが停止されるなど実務面で大きな制裁もあります。
- 行政による事業停止・許可取消: 不法就労が発覚した企業には、行政指導により是正勧告や事業停止命令が出される場合があります。派遣会社の場合、不法就労助長で有罪になれば労働者派遣事業の許可取消しという厳しい処分が下されることがあります。また技能実習生や特定技能外国人の受入企業が入管法違反を犯すと、実習計画の取消しや5年間の受入れ禁止(実習生全員の帰国措置、特定技能は更新不許可)といった行政処分が科されます。これは当該企業にとって事実上の業務停止命令に等しい打撃となりかねません。
- その他の罰則例: 外国人雇用状況の届出を怠った場合は30万円以下の罰金の対象となります。社会保険未加入についても前述のとおり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。労働基準関係法令違反については内容に応じて6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(例えば最低賃金法違反や労基法の罰則規定)などが科せられ、重大な労働違反企業は企業名公表や書類送検の対象となります。行政は監督指導による是正勧告を経ても従わない悪質事案について、積極的に刑事告発を行う姿勢を強めています。
以上のように、法令遵守を怠った場合のペナルティは刑事罰・行政処分・社会的信用の失墜と多岐にわたり、企業経営を揺るがします。外国人材の受け入れにはリスクに見合った慎重さと法令知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では外国人の雇用をお考えの事業主の方からの相談も受け付けています。
お問い合わせはこちらからどうぞ。