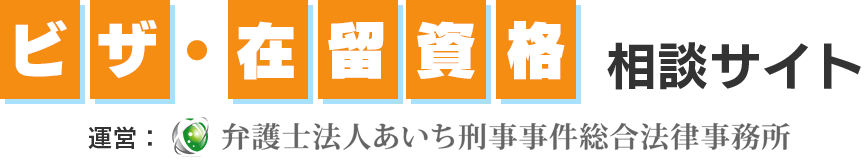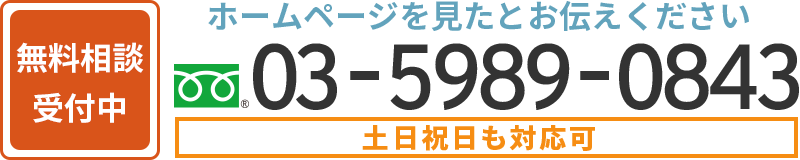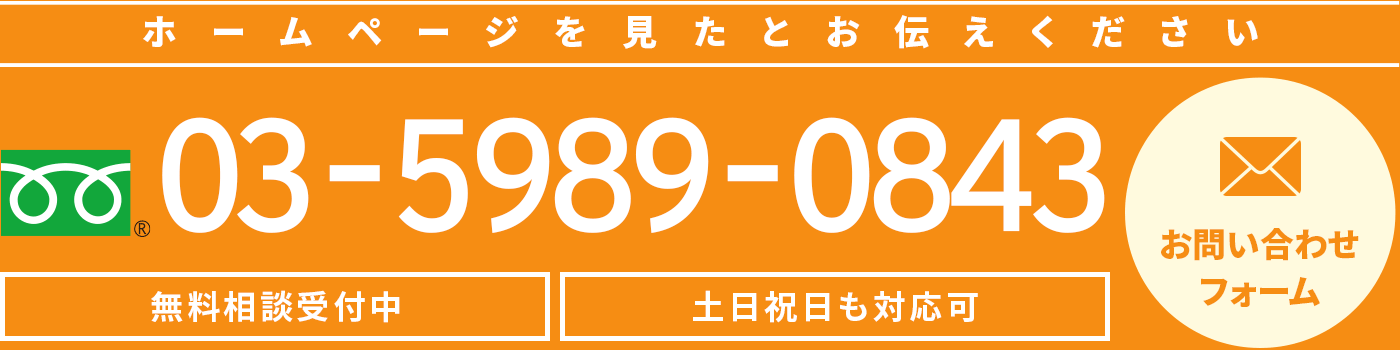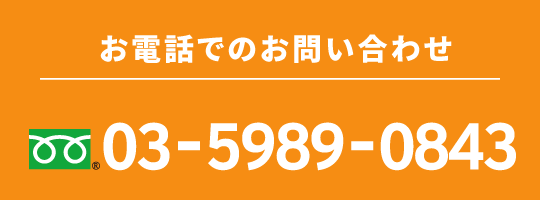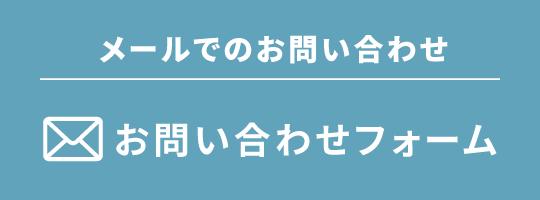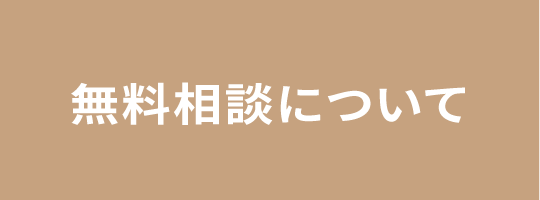このページの目次
はじめに
日本で働く外国人労働者は年々増加しており、令和6年には約230万人に達し過去最多を更新しました。人手不足が深刻化する中、中小企業でも外国人材を派遣社員として受け入れるケースが増えています。
しかし、外国人を派遣するには日本の法律を正しく理解し、遵守しなければなりません。対応を誤れば「不法就労助長罪」という重大な犯罪に問われ、企業存続に関わるリスクを抱えることになります。
本記事では、労働者派遣法と入管法に基づく外国人派遣の注意点を解説し、具体的な違法事例や防止策を紹介します。
外国人派遣に関係する主な法律
労働者派遣法
労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と労働者の保護を目的としています。派遣事業を営むには国の許可が必要であり、派遣できる業務や契約期間にも制限があります。
無許可派遣や「偽装請負」は違法であり、摘発されれば事業停止や許可取消といった厳しい処分が下されます。
入管法
入管法は、外国人の在留資格や就労可否を規定しています。とくに重要なのが「不法就労」です。
不法就労とは、就労資格のない外国人を働かせることや、在留資格で認められていない業務に従事させることを指します。企業がこれに関与すれば、不法就労助長罪に問われます。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、外国人を不法就労させたり、その周旋をした事業者を処罰する法律です。
特徴は以下のとおりです。
- 故意だけでなく「確認不足」でも処罰対象
- 「知らなかった」では通用しない
- 2024年法改正により罰則が強化
- 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 両方が科される可能性あり
さらに派遣の場合、派遣先企業も処罰対象となる可能性があります。派遣元の不備が取引先企業にまで波及するため、信頼関係を損ないかねません。
違法事例に学ぶリスク
- 派遣会社の摘発事例
不法就労状態の外国人を工場に派遣したとして派遣会社が罰金刑を受け、労働者派遣事業の許可を取り消されました。事業継続は不可能となり、会社の存続自体が危ぶまれました。 - 大手企業の書類送検事例
外国人に在留資格で認められていない製造ライン作業を行わせ、会社と担当者が入管法違反で書類送検されました。人手不足を背景に違法就労を容認した結果、企業イメージにも深刻なダメージを与えました。
規模の大小を問わず、違法行為は摘発され厳しい処分が下されます。
外国人派遣で企業が注意すべきポイント
- 在留カードとパスポートの原本確認
在留資格の種類・期限・就労制限を必ず確認。偽造・無効カードに注意。 - 派遣先業務との適合性確認
在留資格で認められた範囲の業務か事前にチェック。必要に応じて資格変更を検討。 - 就労時間の遵守
留学生や家族滞在の資格は週28時間まで。超過勤務は不法就労につながる。 - 適法な契約形態の維持
無許可派遣や偽装請負は禁止。技能実習生・特定技能など派遣禁止資格での就労も不可。 - 行政手続と法改正対応
外国人雇用状況届出を必ず提出。法改正の最新情報を把握し、社内規程を更新。
専門家に相談する重要性
外国人派遣は人材不足の解消に有効ですが、法的リスクも大きい分野です。
「この業務は派遣して大丈夫か?」
「資格外活動に当たらないか?」
といった疑問が出た際は、早めに弁護士へ相談することでリスクを回避できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、外国人に関する刑事事件や不法就労助長罪の対応実績が豊富です。違反を未然に防ぐための体制づくりや、万一のトラブル発生時の迅速な対応をサポートしています。
まとめ
- 外国人派遣は有効な人材活用手段だが、法令遵守が最優先
- 不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされず、罰則も厳格化
- 適切な確認と管理体制が企業防衛につながる
- 不安があれば専門家に相談を
外国人人材を安心して活用するために、今一度自社の体制を見直してみてください。