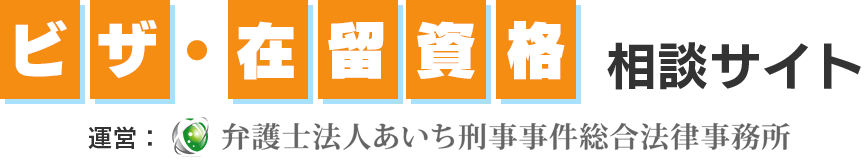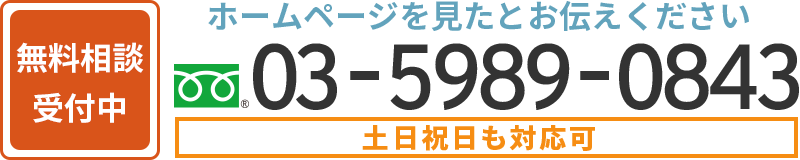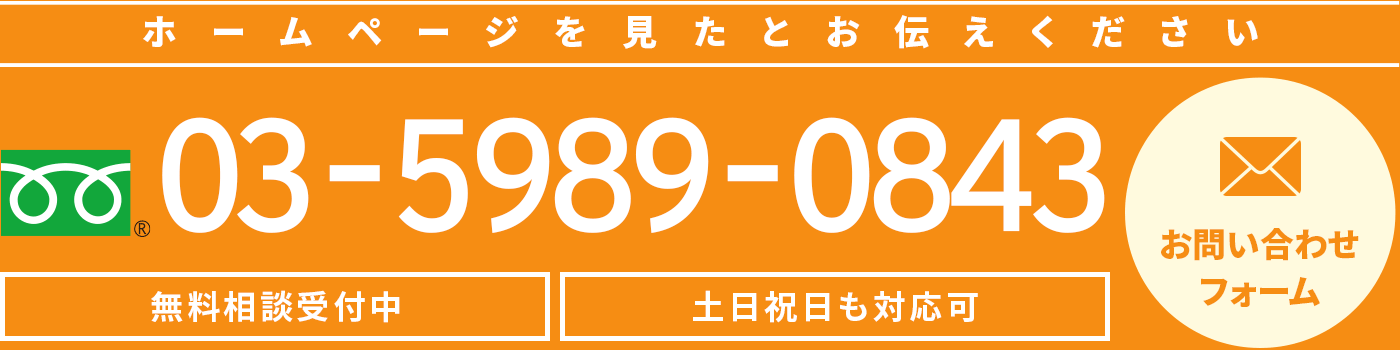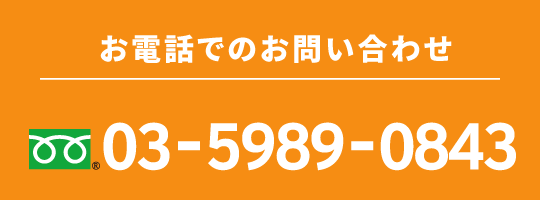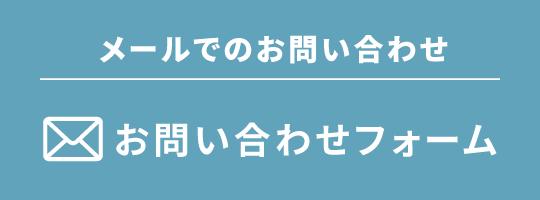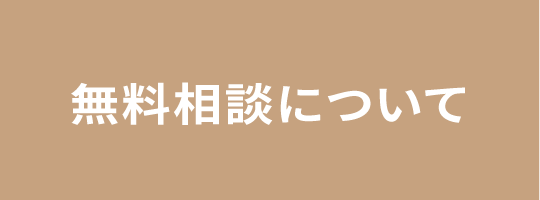「育成就労制度」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
2018年の入管法改定(翌19年施行)によって、深刻な労働力不足に対応するために、在留資格「特定技能」が創設されました。
ニュース報道:外国人材「育成就労」新設、技能実習を改革 閣議決定
特定技能には、最長5年間で、家族の帯同が認められていない1号と、家族帯同が可能で、通算在留期間に制限のない2号があります。
技能実習制度に替わる「育成就労制度」は、未熟練労働者として受け入れた外国人を、特定技能1号に移行できる水準に育成しようというものです。
つまり、外国人の出身国のためではなく、受入れ国である日本の労働力不足解消に資するよう、育成しようという制度です。そのため、新制度の受入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」に一致させるとしています。
また、現行制度の下では、良好な技能実習2号修了者は、無試験で特定技能1号に移行できますが、新制度では、日本語と技能の試験に合格しなければ移行できません。
つまり、育成の結果、一定レベルに達しない外国人は帰国しなければいけません。特定技能1号から2号への移行にも日本語と技能の試験があります。
やはり、一定レベルに達しなければ、帰国してくださいという制度設計です。
今回の見直しの最大の争点は、転籍の自由です。「育成就労制度」では、転籍要件が緩和され、自己都合の転籍が認められるようになります。
しかしながら、同一受入れ機関での1年を超える就労、日本語と技能試験の合格などの要件が設定されることで、一定の転籍制限が維持されています。もちろんですが、たとえ要件を満たしたとしても、転籍先が見つからなければ転籍できません。
現行制度でも、やむを得ない事情がある場合には、転籍が認められていますが、監理団体や技能実習機構による転籍支援はうまく機能しておらず、外国人の権利保護という観点からすれば、転籍が実質的に保証されない限り、技能実習制度の問題点が継承されてしまう可能性が高いといえます。
これに対して、受入れ機関や地域からは、転籍要件が緩和されることで、賃金などの労働条件の良い都市部へ外国人が流出してしまうことを危惧する声があがっています。
有識者会議の最終報告書では、転籍要件の就労期間に関して、当分の間、受入れ分野によっては1年を超える期間を設定することを認めるといった受入れ機関や地域に対する「配慮」とも言える経過措置が示されています。
加えて、送出し機関、監理団体、技能実習機構などの現行の技能実習制度に係る関係諸機関が、新制度においてもすべて維持されています。
かつての日本は、受入れ国として絶対的に優位な地位にあり、多くの外国人を惹きつけることができましたが、近年では、もはや外国人にとっての移住の選択肢は日本だけではありません。
今後の日本が目指すべきは、制度によって縛らなくても、選ばれる地域をつくることだと思います。
受入れ機関や自治体、地域住民やNPOなど多様なアクターが連携・協力し、就労環境や生活環境を改善・整備し、魅力を高めるための努力をすることが必要不可欠でしょう。