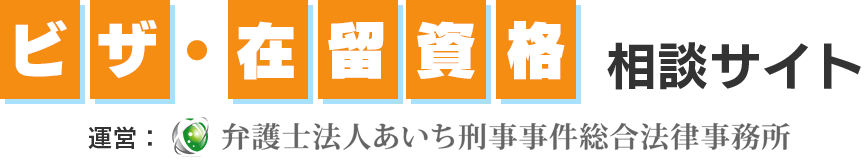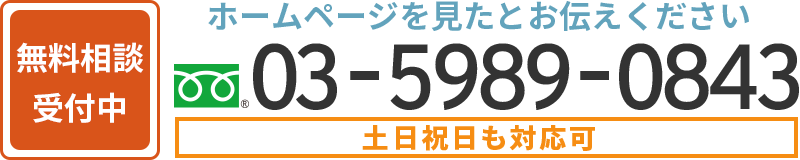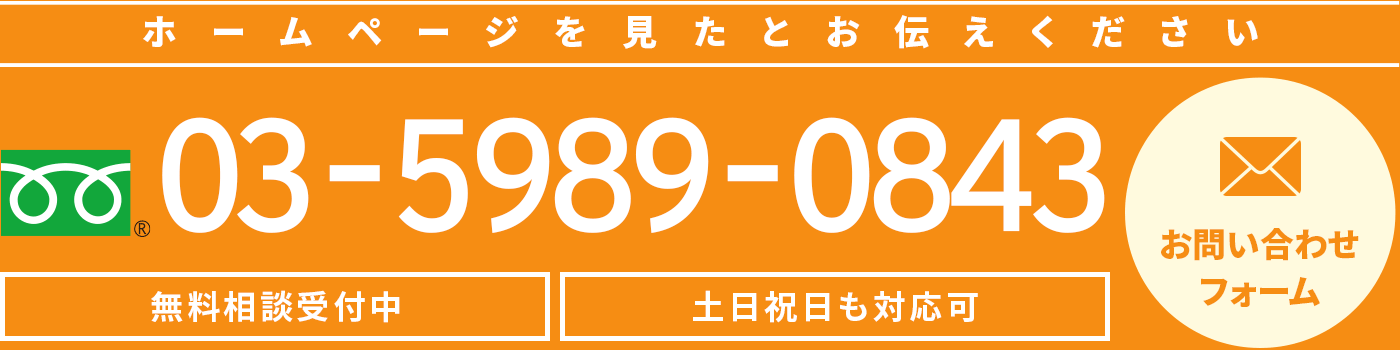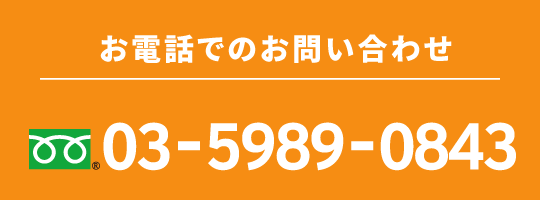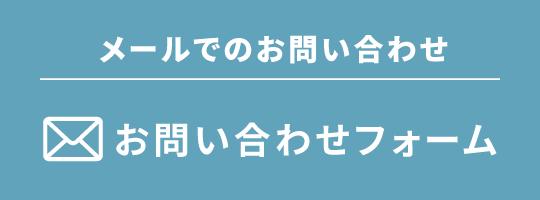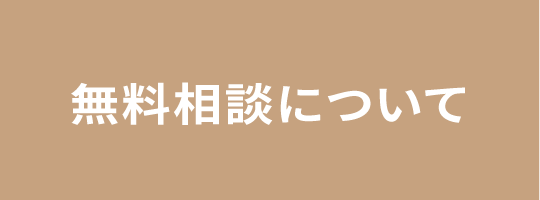このページの目次
事例
(架空の事例です)
Aさんは某県に在住している日本人男性です。10年前に会社を定年退職して、現在は年金暮らしをしています。
7年前に前妻と離婚し、5年前にB国籍の女性CとSNSを通して知り合い再婚しました。妻のCさんはA さんと結婚して3年後に念願の永住資格を取得しました。
Cさんは永住資格を取得するとすぐに実母の面倒を見てくると行ってB国に帰国しました。以降年に1回ほど妻はB国から日本に戻ってきますが、
1か月ほど日本に滞在してすぐにB国に戻ります。CさんはB国で現地の男性パートナーDさんと一緒に暮らしているようです。
AさんがCさんにこの件を問い合わせると弟と一緒に暮らしていると言います。しかしAさんがCさんと結婚するまで彼女に弟はいませんでした。
AさんはCさんと離婚したいと考えていますが、離婚にあたって日本の法律は適用されるのでしょうか。
1.適用される法律
日本人と外国人のカップルが離婚した場合、離婚に関してどちらの国の法律が適用されるか、国際結婚のカップルが離婚手続きをするにあたり、離婚手続きに関して日本の法律と配偶者の国の法律のどちらが適用されるかが問題となります。
この場合に日本の法律と海外の法律のどちらを適用させるかは「法の適用に関する通則法」により判断されます。
①法の適用に関する通則法25条(婚姻の効力)
「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦の最も密接な関係がある地の法による。」
②法の適用に関する通則法第27条(離婚)
「第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」
法の適用に関する通則法27条により、離婚については法第25条の規定が準用され、本ケースでは離婚にあたり夫であるAさんの常居所である日本法が適用されます。
2.離婚の種類
日本の法律では離婚の方法として①協議離婚②離婚調停③審判離婚④裁判離婚の4種類が定められています。
AさんとCさんの間で離婚の合意がまとまれば、戸籍法の定めるところに従い離婚届を提出することによって離婚が成立します。協議離婚(民法763条、739条、戸籍法第76条、第77条)。
AさんとCさんの間で離婚の合意がまとまらず、なおAさんがCさんと離婚を望む場合、Aさんは管轄の家庭裁判所に対して離婚調停の申立てを行うことになります。
逆にCさんの方から日本の法律に従いAさんとの離婚を求めていくことも可能です。
(法の適用に関する通則法第27条)
3.離婚後の在留資格
永住者の場合離婚しても離婚の事実は永住資格に影響しないので、Cさんは離婚しても永住資格は変りません。Cさんは離婚後に再婚することも自由です。
CさんがB国で同棲しているDさんと再婚した場合、CさんはDさんを「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に呼寄せることが可能です。
DさんはCさんと実態の伴った結婚を3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいれば永住許可申請の居住要件を充足します。
そのためDさんはCさんと結婚して最短で3年で日本での永住資格取得が可能となります。このように「日本人の配偶者等」の在留資格は在留制度上大変有利な資格となっています。
永住資格目的で日本人との国際結婚を望む場合があることも十分予測されます。
本ケースのAさんのように外国人配偶者が永住資格を取得したら急に冷たくなり離婚せざる負えない事態に追い込まれることは決してあり得ないことではありません。
Aさんのような事態にならないためには、特に再婚、再再婚で国際結婚をされている日本人の方は、永住資格は日本で暮らす外国人にとって、今まで自分が認識していたよりもはるかに重要で心強い在留資格であることを再認識する必要があるでしょう。
具体的な手続きやビザの相談,お問い合わせはこちらからどうぞ。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。