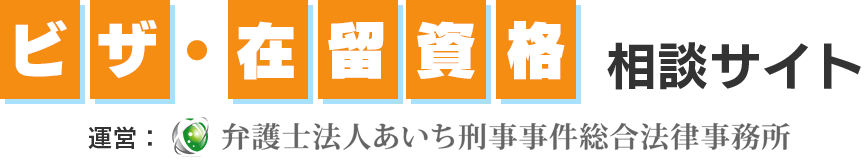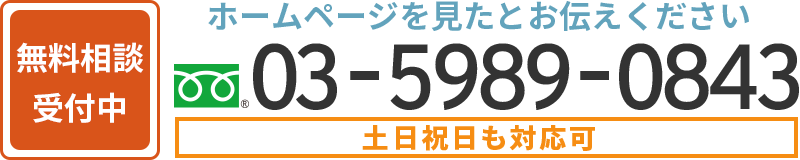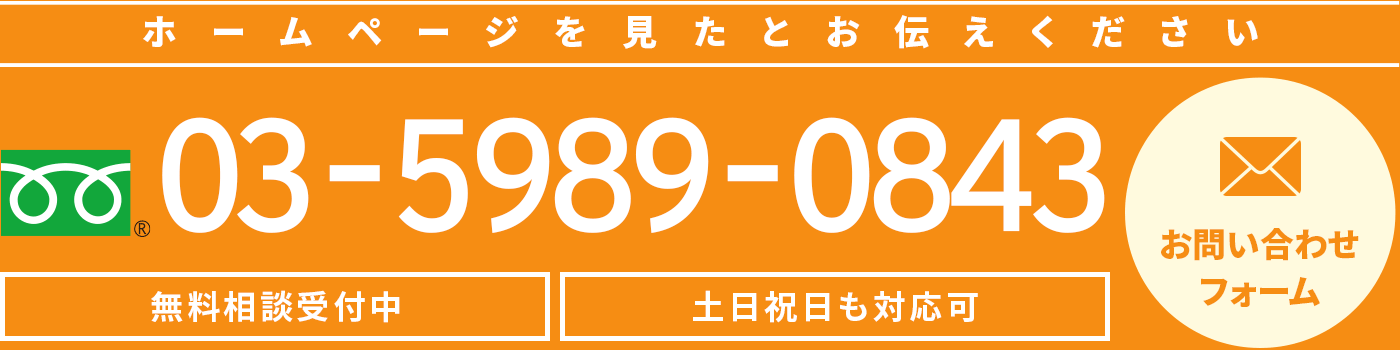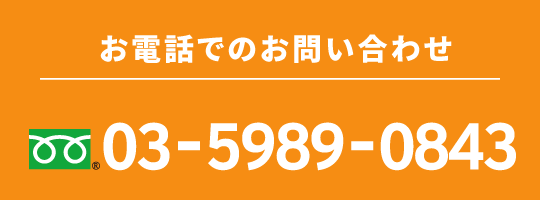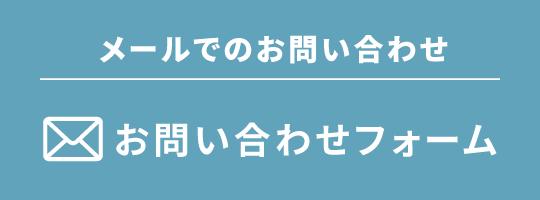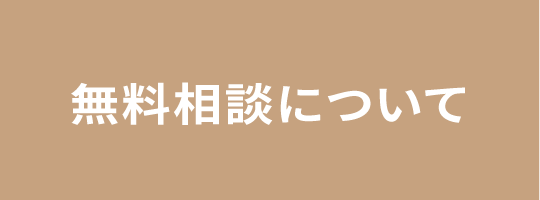Archive for the ‘入管法,法改正その他’ Category
永住許可申請におけるセルフチェックシート

永住許可申請での永住許可セルフチェックシートの提出について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
令和6年12月から永住許可申請で永住許可セルフシートの提出が求められるようになりました。
出入国在留管理庁HPには、永住許可セルフチェックシートに関して以下のような内容が記載されています。
(重要1)
提出書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。以下のチェックシートで在留資格や身分・地位に応じた資料を確認の上、提出してください。
・ 提出書類チェックシート(日本人の配偶者)
・ 提出書類チェックシート(日本人の実子)
・ 提出書類チェックシート(永住者又は特別永住者の配偶者)
・ 提出書類チェックシート(永住者又は特別永住者の実子)
※ 提出書類が不足していた場合は、追加資料を求めることとなり、資料が揃うまで審査を進めることが困難となります。
そのような場合は、書類が揃っている方の審査を優先的に行うこととなりますので、御承知おき願います。
(重要2)申請前に、永住許可の要件に該当するか、以下のチェックシートで確認してください。
・ 永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」用)
※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
※ 「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
※ 申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、本チェックシートも以下の書類と合わせて提出いただきますようお願いいたします。
セルフチェックシートの内容
チェックシートの内容は概ね次の通りです。
永住許可申請セルフチェックシート【在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方】
・永住許可の要件に該当するか、事前に確認していただくためです。
・以下の質問について、「はい(YES)」か「いいえ(NO)のいずれかに「〇」をつけてください。
* 一つでも「いいえ(NO)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
(「いいえ(NO)が一つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
1.(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の配偶者である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、)日本に引き続き1年以上在留している。
はい(YES) いいえ(NO)
2.直近3年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、
住民税を適正な時期に納税している。 はい(YES) いいえ(NO)
*未納や当初の納税期間を超えて納税したことがある場合は、あなたの扶養者の納税状況を回答してください。 はい(YES) いいえ(NO)
3.国税(源泉所得税及び復興所得税特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の未納がない。 はい(YES」) いいえ(NO)
4.直近2年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、
、年金保険料(国民年金及び厚生年金)を適正な時期に納付している。 はい(YES) いいえ(NO)
5.直近2年間(あなたが日本人、永住者又は特別永住者の子である場合は、直近1年間)、医療保険(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)を適正な時期に納付している。
はい(YES) いいえ(NO)
6.現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されている。
はい(YES) いいえ(NO)
7.過去に、日本国の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。
はい(YES) いいえ(NO)
これら1から7の項目に「はい」または「いいえ」をチェックして年月日を記入・署名の上、他の永住申請書類と一緒に入管に提出します。
1から7の項目の中で、従来の永住申請からの変更部分として2.4.5に(適正な時期に)の文言が追加されています。
住民税、年金保険料、医療保険料の支払いについての必要納付期間については従来通りですが、これらの「公租公課」を「適正な時期に納付していること」が追加され、住民税や年金保険料といった「公租公課」の支払いが例え一回でも納付期限に遅れると永住申請が不許可になる可能性が高くなるということが明記されました。
なぜチェックシートが導入されたのか?
永住許可セルフチェックシート導入の背景として以下の2点が考えられます。
①永住許可申請の審査期間長期化の解消
現在品川にある入管では永住申請から審査結果が出るまでに1年以上かかっています。コロナ禍での自粛期間が終了したことに伴い首都圏を中心に永住申請が増加しており、入管での永住審査が追いついていかないことが原因と考えられます。そこで申請人が永住申請をする前に自分の申請内容をチェックしてもらい、自ら許可の見込みがないと判断した場合は申請を控えてもらい、
許可の見込みのない申請を減らすことで永住審査をスムーズにすることがあげられます。
②2024年入管法改正での公租公課未払いによる永住資格取消事由追加との整合性
2024年入管法の改正で入管法第22条の4第1項8号の「故意に公租公課の支払いをしないないこと」が永住資格取消事由に追加されました。
この改正と連動して、永住申請における税金の支払いに対して従来よりも要件を厳しくして、対象期間中一度でも納付遅れがあると永住許可が困難であることを永住許可申請者に事前に周知する目的があげられます。
参考:永住許可での「公租公課」の支払いについてのQ&A:永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁HP)
Q 公租公課の不払いが問題なのであれば、日本人と同様に催促や差押えで対応すれば十分であり、在留資格の取消しは永住者に対する過剰な措置ではないでしょうか?
A 永住者については、我が国で生活する上で最低限必要なルールを遵守することが見込まれる者として永住許可を受けているところ、今般の措置は、公的義務を適正に履行せず、在留状況が良好とは評価できないような場合に適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、過剰な措置であるとは考えていません。
Q 改正後の入管法第22条の4第1項8号の「故意に公租公課の支払いをしないこと」とは、具体的にどのような場合を想定していますか?
病気や失業などでやむを得ず支払ができない場合にも、在留資格が取り消されるのですか?
A 「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことをいいます。そして、「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、公租公課の支払をしない場合などを想定しています。このような場合は、在留状況が良好とは評価できず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと考えられます。
他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では永住許可申請を取り扱っています。永住許可申請をお考えの方はぜひ弁護士法人あいち検事事件総合法律事務所までお問合せください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
出国命令制度の法改正,制度はどう変わった?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が令和5年6月9日入管法改正による出国命令制度の変更部分について解説します。
令和5年6月9日の入管法改正により「出国命令制度」が一部改正され令和6年6月10日から施行されています。
「出国命令制度」とは、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続きにより出国させる制度です。」
(出入国管理及び難民認定法、以下法第55条の85)、「出国命令制度」はH16年12月2日に施行されました。
1.出国命令制度設立の背景
出国命令制度が設立された当時不法残留者が219418人いました。
(平成16年1月段階、令和6年1月1日現在では79113人)
不法残留者を減少させることが出入国管理行政における急務の課題でした。
当時からオーバーステイ等を理由に退去強制処分を受けると退去の日から5年は日本に上陸することが認められないとする規定は存在していました。
(退去強制1回目は5年、退去強制2回目以降は10年)
しかしながら不法残留者等を5年又は10年の上陸拒否とする従来からの規定だけでは不法残留者が減少しない状況がありました。
そこで一定の要件を充足し、不法残留の状態にある者が自ら出頭して帰国の意思を示した場合に、上陸特別拒否の期間を5年から1年とすることにより、
不法残留者の出頭を促進し不法残留を減らすことを目的として出国命令制度があらたに制定されました。
2.具体例
具体的に以下の(1)~(5)全てに該当する場合に出国命令が認められます。
(1)ア又はイのいずれかを満たすこと
ア 入国警備官の違反調査の開始前に、速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理局に出頭したこと
イ 入国警備官の違反調査の開始後、入国審査官の違反調査により退去強制事由に該当する旨の通知を受ける前に、
速やかに出国する意思があることを入国審査官又は入国警備官に表明したこと
(2)不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3)窃盗罪等の一定の犯罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
(4)過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5)速やかに日本から出国することが確実と認められること
3.出国命令が認められない場合について
日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬、
大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めなく、日本に上陸することができません。
そのため出国命令制度を利用することはできません。
4.出国命令制度の適用を受けるための出頭場所について
原則として全国に8か所ある地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)又は3か所の地方出入国在留管理局(横浜、神戸、那覇)に出頭します。
5.法改正があった部分
令和5年度の改正では、さらに自発的な出国を更に促す観点から、出国意思をもって自ら出頭した場合に加え、
入国審査官から退去強制事由に該当すると認定される前に速やかに日本から出国する意思を表明した場合にも出国命令の対象が拡大されました。
①(法第24条の3第1項ロ)
「第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、
入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。」
②その他改正による追加事項として、さらに退去強制を受けた者であっても、自分の費用負担で自ら帰国しようとする場合、その者の素行、退去強制の理由となった事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、上陸拒否期間を1年とする決定をすることができることになりました。(法第52条5項)
参考文献:出入国在留管理局HP
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が令和5年6月9日改正の出入国管理及び難民認定法における「出国命令制度」の変更部分について解説しました。
具体的な手続きや事件についてはこちらからお問い合わせください。
「トランプ大統領就任による出生地主義の制限に関する大統領令発付」について

「All persons born or naturalized in the United States,and subject to the jurisdiction thereof,are citizens of the United States and of the State wherein they reside.」
合衆国憲法修正第14条は冒頭で「合衆国内で生まれ、または合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民であり、かつ、その居住する州の市民である」と記し、アメリカ合衆国が出生地主義の原則を定めていることを明らかにしています。
出生地主義とは
出生地主義とは、「父母の国籍の如何を問わず、子が出生によって出生地国の国籍を取得する主義であり、アメリカ、カナダ、オーストラリア及びブラジル等の南アメリカ大陸の多くの諸国で採られて」います。
アメリカ合衆国は国籍の取得にあたり出生地主義を採用する代表的な国の一つです。出生地主義と対になる主義として血統主義があります。
血統主義とは「子がその出生によって出生地の如何を問わず、親の血統に従って親と同じ国籍を取得する主義であり、自国民との血縁関係に基づいて自国の国籍を付与する主義で、フランス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパ大陸諸国をはじめ、韓国、中国などでも原則として採られて」います。日本では子の出生時に父又は母のどちらかが日本国籍であれば子に日本国籍を認める父母両系血統主義を採用しています。
*逐条詳解 国籍法P106
新大統領令の内容は
トランプ大統領は大統領就任初日の2025年1月20日、合衆国憲法修正第14条で定められた出生地主義の適用をこれまでより大きく制限する大統領令に署名しました。
日本経済新聞 トランプ氏、「出生地主義」制度見直しの大統領令に署名
大統領令では出生地主義の制限にあたり、合衆国憲法修正第14条の冒頭にある「合衆国の管轄に服する者」という文言を重要視しています。
大統領令によると、元々合衆国憲法修正第14条はアメリカ合衆国国内で生まれた全ての人に生来的に市民権を与えるものではなく、アメリカ合衆国の「管轄に服さない者」は出生地主義による市民権の付与の対象から除外しているという理解に沿って、アメリカ国籍法コード8 U.S.C1401では「アメリカ合衆国で生まれその管轄に服する者」が出生時からアメリカ合衆国の国民及び市民であると規定しています。
今回の大統領令ではアメリカ合衆国で生まれながらもアメリカ合衆国の市民権が認められない者の範囲として、以下(1)、(2)をあげています。
(1)子の出生時に子の母親がアメリカ合衆国に不法滞在しており、子の父親が子の出生時米国市民又は永住者ではない場合。
(2)子の母親が子の出生時に適法な滞在ではあるが滞在が一時的なものである場合、例えばビザの免除を受けアメリカ合衆国の支援を受けての訪問、就労ビザ、留学ビザ、観光ビザ等の場合や子の父親が子の出生時にアメリカ合衆国市民や永住者ではない場合。
(1)及び(2)に該当する場合は、合衆国憲法修正第14条で定められた「アメリカ合衆国の管轄に服する者」に該当しないとして、子がアメリカ合衆国で生まれても自動的にアメリカ国籍を付与することを認めないとするものです。
この措置はアメリカ合衆国が採る出生地主義を否定するものではありませんが、従来よりも出生地主義による国籍付与の大幅な制限となるものです。
この大統領令は、大統領令の発令日より30日経過後からアメリカ合衆国国内で子が出生した場合に適用されます。大統領令発付即日から、この大統領令は合衆国憲法修正第14条に反し違憲であると提訴がありました。
この大統領令が出生地主義について定めた合衆国憲法修正第14条に反するか否かについては現段階ではまだはっきりしていません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日本国籍取得・帰化申請を取り扱っております。
日本国籍取得・帰化申請でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
一度限りで在留特別許可?報道記事を解説
「令和6年6月10日に施行された改正入管法に伴う今回限りの在留特別許可について」あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

まずはこちらの参考報道をご覧ください。
子ども212人、在留特別許可 人道上配慮で日本生まれ外国人に(共同通信) Yahoo!ニュース 9/27(金)12:03
出入国在留管理庁は27日、在留資格がなく強制送還の対象となり得る18歳未満の外国籍の子ども212人とその家族183人に、法相の裁量で例外的に在留を認める「在留特別許可」を付与したと発表した。
日本で生まれ、学校に通っている児童・生徒で、親に犯罪歴がない場合などは、人道上の配慮から今回に限って特例的に家族を含めて付与する方針を示していた。
入管庁によると、改正入管難民法が施行された今年6月10日までの時点で対象の子どもは263人いて、このうち212人に付与。11人が自らの意思で帰国し、40人が親に不法入国といった犯罪歴があることや、就学年齢に達していないなどの理由で付与されなかった。
212人の在留資格の内訳は、「留学」が155人で、「特定活動」が29人、「定住者」が23人など。不法残留などで退去を求められても帰国を拒む外国人の中には、日本の学校で学び、日本語しか話せない子どもも多い。国会審議などで人道的配慮を求める声が上がり、斎藤健前法相が昨年8月、家族も含めて付与する方針を表明した。
こちらの記事をもとに解説をします。
令和5年6月9日、出入国管理及び入管改正法が抜本的に改正され、令和6年6月10日に施行されました。
改正の重要な目的の一つとして送還忌避者の問題解決がありました。
新しい入管法では,「送還停止効の例外規定」というものが設けられています。
「送還停止効の例外規定」とは、退去強制処分を受けている者でも難民申請をしている間は送還が一時的に停止されるという規定です。
新しい入管法ではこの規定に例外を設け、①3回目以降の難民申請者、②3年以上の実刑前科者、③テロリスト等は難民等と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出しなければ、強制送還の一時停止効を認めないというものです。
送還忌避問題と関連して、政府は令和6年6月10日 施行の出入国管理及び難民認定法の改正に伴う送還忌避者の一部に今回限りの在留特別許可を実施しました。
在留特別許可の対象となったのは、日本で不法滞在の状況にある日本で生まれ学校に通っている外国籍の子とその家族合わせて212人、その内訳は「留学」が155人、「特定活動」が29人、「定住者」が23人でした。
「留学」の155人は日本の小学校、中学校等に通学する外国籍の児童が対象となり、「特定活動」29人と「定住者」23人は主に学校に通っている児童の家族に許可されました。
今回の在留特別許可の実施については、出入国管理及び難民認定法改正と関連して以下のような事情がありました。
令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者4,233人のうち本邦で出生した子どもは201人いました。現行法上、法務大臣の裁量的判断により、在留特別許可は可能であることから養育する親に在留を特別に許可する事情がない場合には、基本的に子どもにも在留特別許可を認めていませんでした。
そこで子どもと親を家族一体として扱い子どもと親に在留を特別に許可する事となりました。
令和5年6月9日に改正された入管法改正法により、庇護すべき者は適切に庇護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能になる結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化する子どもの増加を抑止することが可能となりました。
(送還停止効の例外規定の実施により、難民であることについて相当の理由がある資料 を提出できない難民申請者を速やかに帰国させるため) 既に在留が長期化した子どもに対して、現行法で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して今回限りの特例措置として、家族一体として在留特別許可をして在留資格を与える方向で検討をしました。
在留特別許可の対象は、改正法施行時までに、本邦で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦で生活 をしていくことを真に希望している子どもとその家族です。ただし、在留特別許可は親に看過し難い消極事情がある場合を除かれます。
(注1)看過し難い消極事情とは、①不法入国・不法上陸、②偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理 行政の根幹に関わる違反、③薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、④懲役1年超の実刑、⑤複数回の前科を有していることを想定しています。
(注2)看過し難い消極事情があっても、個別の事案ごとに諸般の事情を総合考慮して在留特別許可をする場合もあり得ます。
本方針により、本邦で生まれ育った在留資格のない子ども201人のうち、自らの意思で帰国した者を除き、少なくとも7割、就学年齢に達している子どもの8割程度に在留特別許可をすることが見込まれます。
今回行われた日本で生まれ在留資格のない子どもに対する在留特別許可は、あくまで今回限りの特別措置であり、次回以降、在留資格のない子どもの在留特別許可は個別に審査されることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、在留資格のない子どもの在留特別許可を扱っています。お子様の在留資格でお悩みの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせはこちらからどうぞ。
監理措置とは何なのか
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、2024年6月10日施行の改正「出入国管理及び難民認定法」に新たに創設された「監理措置制度」について解説します。
昨年の入管法改正では3回目以降の難民者は強制送還の対象になるという部分が大きな話題となりましたが、それ以外にもいくつか重要な改正や新規創設がなされました。
その中の一つに監理措置制度があります。
監理措置とは、「退去強制手続を受ける外国人について、監理人による監理の下で逃亡等を防止するとともに相当期間に渡って社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進めるという措置」とされています。 *出入国在留管理局HP
これまで不法入国の場合や日本滞在中に何らかの事情により在留資格を失って国外退去が確定した者は、国外退去するまで入管収容施設に収容することを原則としていました。(全件収容主義)
全件収容主義の問題点として、国外退去が確定しても退去強制命令を拒み続ける外国人がいた場合、その外国人は長期に渡る入管施設への収容につながり、結果として被収容者の健康上の問題等が生じることがありました。
また被収容者の健康問題を考慮して仮放免を行った場合に、仮放免を受けた外国人が逃走するという事態が生じることもありました。
そこで問題点が多かった原則収容の入管法の規定(全件収容主義)を全面的に見直して、個別事案ごとに逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮したうえで収容の要否を見極めて、収容か監理措置かを個別に判断することになりました。
新しい入管法から見た監理措置の流れ
(違反調査)27条
入国警備官は、退去強制事由に該当すると思われる外国人「(以下容疑者)」がいるときは、容疑者に対して退去強制事由に該当する事実があるかどうかを調査することができます。
(主任審査官の審査)39条1項
入国警備官は第27条による違反調査の結果、容疑者が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認める場合は、容疑者が逃走する恐れがあるとして収容した場合を除いて主任審査官に、容疑者が退去強制事由に該当する相当の理由がある旨を通知します。
第39条2項(主任審査官の審査)
入国警備官から通知を受けた入国審査官は、容疑者が入管法24条各号で規定する退去強制事由のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、
第44条1項の規定による監理措置とするか入管施設に収容するかを審査しなければなりません。
(収容に代わる監理措置)第44条の2項
第39条2項による調査の結果、主任審査官は容疑者が入管法第24条各号(退去強制該当事由)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合に、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、容疑者を収容しないで退去強制の手続きを行うことが相当であると判断する場合は、容疑者を監理措置に付ける旨の決定をすることになります。
第44条の2第4項
入管法に定める規定により入管収容施設に収容された容疑者は、法務省令で定める方法により、主任審査官に対して、自分を監理措置に付けるよう主任審査官に請求することが出来ます。
第44条の2第6項
主任審査官は容疑者からの請求(法44条の2第4項)又は職権で、収容されている容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により収容されている容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、容疑者を収容施設から放免(入管収容施設から外に出すこと)して退去強制手続きを行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付ける決定をします。
この場合、監理措置に付ける者に対して監理条件を付けることができ、また監理措置につけた者が逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要がある場合は、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付されることができます。
以上が改正入管法で新たに創設された監理措置について条文から見た流れです。
送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する政府方針について

令和5年8月に出入国在留管理庁が発出した「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」という方針を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.送還停止効にある難民申請3回目以降の人の強制送還を可能にする入管法改正が、2023年6月9日に国会で成立しました。
政府は改正に伴い強制送還の対象となっている日本生まれの小中高生と親を対象に今回限りの特例として、子と親を家族一体として在留特別許可をして在留資格を認める方針
「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」を表明しました。
対象となるのは、改正法施行(令和6年6月10日)までに、日本で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを強く希望している子どもとその家族です。ただし、親に「見逃しがたい消極的事情」がある場合を除きます。
見逃しがたい消極的事情として以下の5つの事項があげられています。
①不法入国・不法上陸②偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国管理行政の根幹機関わる違反、③薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、④懲役1年以上の実刑⑤複数回の前科刑を有している場合、の5つです。
但し見逃しがたい事情があっても、個別の事案毎に諸般の事情を総合考慮して在留特別許可を認める場合もあります。
2.在留特別許可を認める子どもと認めない子どもについて
令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者は4,233人でした。
そのうち「日本で生まれ育った」在留資格のない子どもは201人で、自らの意思で帰国した者を除き、
少なくともそのうちの7割、就学年齢に達している子どもの8割程度に在留特別許可をすることが見込まれています。
以下在留特別許可が認められる子と認められない子の内訳です。
強制送還を拒否している外国人4233人
↓
このうち18歳未満の子どもは295人
↓
日本以外で生まれた子(救済対象外)94人
+
子が日本で生まれたが、親が不法入国・不法上陸、
懲役1年以上の実刑等(救済対象外)約60人
↓
295-(94+60)=140
約140人の子供が救済対象となる見込みです。 子どもの在留資格は「留学」となります。
3.在留を認める子どもと認めない子どもの線引きについて
①子どもが日本で生まれたか否か
②親が受けた刑事処分や行政処分の軽重
子どもの在留特別許可の認定基準について、①と②の判断基準が示されています。
①に対しては子どもが日本で生まれたか否かという本来子どもにとってなんら関係のない事情で線引きされています。
国籍について出生地主義(血筋によらず生まれた場所が自国内であれば国籍を認める)が取られている国々がありますが、日本は出生地主義ではなく血統主義(両親のどちらかが日本国籍であれば日本国籍を認める)を採用しており、なぜ子どもが生まれた国が日本であれば在留特別許可を認め、そうでない場合は最初から在留特別許可を認めないのか、その判断基準が漠然不明確な部分があります。
4.親の刑事処分や行政処分の軽重
仮に日本生まれの子どもであっても親の犯罪歴や行政処分歴により在留特別許可が認められるか否かが決まるという点についてですが、親が品行方正な不法滞在者であれば子の在留資格を認め、そうでない場合は子どもの在留資格を認めないということで、子どもの在留資格は親の在留状況次第、まさに親ガチャで決定されるということになります。
子の在留特別許可を認めるか否かは、子にとって一生を左右する重大事である以上、①子が日本で生まれたか否か、②親の犯罪歴、行政処分違反歴の軽重といった形式的判断によるのではなく、子ども一人一人の個別具体的・実質的判断によるべきと思います。
また今回の在留特別許可が入管法の大改正による一回限りの特例であるなら、在留特別許可を認める子どもの対象は出来るだけ広くすべきでしょう。
参考:東京新聞WEB版 2023年12月18日付
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では在留特別許可についても取り扱っています。
仮放免や在留特別許可についてお悩みの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
再審情願について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が再審情願について解説します。
(架空の事例です)
A君とB子さんは南米にあるC国出身の恋人同士です。ともに20代前半でお互い小学校低学年の頃に日系2世の両親に連れられて日本に来ました。
2人は小学校・中学校まで一緒の学校で二人は幼馴染でした。
A君は中学卒業後、両親の都合でいったん家族と一緒にC国に帰りましたが、最近また日本に戻ってきました。今度は単身での来日で、A君はD県にある大手自動車部品メーカーに派遣社員として働くことになりました。
B子さんは現在D県にある有名国立大学の4年生で、昨年日本国籍を取得しました。
来春から地元の大手自動車メーカーのT社に就職も決まっています。
2人は昨年5年ぶりに再会して恋人同士になりました。
2人はB子さんが大学を卒業したら結婚しようと誓い合いました。
2人が交際を始めてから2年目の夏、A君はお盆期間で会社が長期連休の時に市内の繁華街にあるクラブに友達と遊びに行きました。
少し羽目を外してお酒を飲み過ぎたので、酔い覚ましに友達と入った喫茶店で、たまたま店にいたお客さんとささいなことで口論となり、思わず相手を殴ってしまいました。
A君は体が大きく相手が小柄だったこともあり、相手の鼻を骨折させてしまいました。
相手側が骨折した診断書を警察に提出したこともあり、A君は傷害罪で起訴されました。
A君は裁判所で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。A君は控訴することなく判決は確定しました。
判決の日から3か月後がA君の在留期間の満了日でした。
A君は在留期間満了日の20日前に自分の在留更新申請手続きを行いましたが、在留期間経過後に入管から在留更新結果の通知が来ました。
A君は入管からの通知のハガキを持って出頭しました。
A君の在留更新申請は不許可でした。A君は在留申請不交付通知を受けたのち、その場で帰国準備の為の特定活動30日に在留資格変更手続きをしましたが、A君は既に仕事をやめていて所持金がないこともあり、結局C国行きの航空チケットを買わずに帰国することなく特定活動の30日間が過ぎてしまいました。
その後A君は入管から呼び出しがあり入管に出頭したところ、A君は入管施設には収容されずに仮放免となりました。それからA君は毎月1回入管に出頭していましたが、入管に出頭を始めてから半年後、いつものように入管に出頭したところ、そのまま入管施設に収容されてしまいました。
入管施設に収容されてしばらくしてからA君に退去強制命令が発布されました。
退去強制命令がA君に出された後、B子さんがA君の監理人となりA君は入管の収容施設から出てB子さんと一緒に暮らし始めました。
A君としてはB子さんと結婚の約束をしているし、C国に帰ったら無期限で日本に入国できないと知人から聞いていたので、A君は絶対にC国に帰りたくありません。
B子さんもA君を帰国させたくありません。
A君が日本に残ってB子さんとの生活を続けていくためにはどうしたらいいのでしょうか?
A君は退去強制命令を受けているので、このままでは日本に残ることができません。
いずれ退去強制手続きが執行され、A君は日本を離れることになります。
A君が日本に残るためには入管に在留許可を認めてもらう必要があり、A君が日本に残るための申請手続きとして、再審情願という手続きがあります。
再審情願とは
再審情願とは、退去強制発布処分後に事後的に生じた事情に鑑み、適法になされた当該処分を撤回して日本での在留を認めなければ人道上極めて問題であるといえる場合に、法務大臣に退去強制処分を撤回して在留を特別にお願いするものです。
法律によって手続きが定められているものではなく,あくまで法務大臣が裁量によって処分を撤回して在留を認めるという例外的な手続きです。裁判上も,法務大臣が再審情願に対して何かしらの回答をする義務までは認められていません(参考判例平成26年1月30日判決)。
具体例として日本人と恋愛関係にある外国人が日本人の交際相手と結婚を予定していたところ、何らかの理由で在留資格を失ってしまい、退去強制処分が出る前に婚姻手続きが間に合わず、退去強制処分後になって婚姻手続きが成立した場合等があげられます。
A君、B子さんのケースでは、まず第一にA君、B子さんの結婚手続きを済ませることが必要です。
B子さんは日本国籍なので、AさんはB子さんと結婚して「日本人の配偶者」となり、「日本人の配偶者等」の在留資格を認めてもらう申請をします。
A君の再審情願を認めるかどうかは法務大臣の裁量となりますが、再審情願の裁量は在留特別許可を判断する時の法務大臣の裁量よりも広いとされています。
従って再審情願を認めてもらうためには、単にA君とB子さんの2人が結婚したという事実のみを伝えるのではなく、結婚に至ったいきさつや動機も含めて、本来退去強制処分が発布されて本国に帰国しなければならないA君が、なぜ日本に残ることが必要なのかを丁寧に訴えていく必要があります。
理由書を作成してA君の在留許可の必要性を訴えたり、家族や知人に嘆願書を書いてもらうことも必要かもしれません。本ケースではB子さんはまだ大学生で就職しておらず、就職しない段階で結婚して再審情願をしても、2人は独立して生計を立てていく能力が乏しいと判断されるかも知れません。
そこでB子さんが就職して給料を得るようになってから再審情願を行うなど、2人が結婚してから生活できる経済力があることを示すことも重要になります。
またA君の在留許可が認められるまではA君は仕事ができません。
そこでA君が仕事が出来ない間は、B子さんがA君を養っていく必要があります。いつA君の在留許可が認められるかわからない状況で、B子さんが1人でA君の面倒を見ていくのは大変ですが、お互いの真摯な愛情を入管に伝えることができれば、A君の在留許可が認められるチャンスはあると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では再審情願による申請手続きを扱っています。
現在仮放免等で再審情願による申請手続きをお考えの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。ご相談を希望する方は,こちらからお問い合わせください。
在留特別許可のガイドラインの改正について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、令和6年3月に改定され,同年6月10日から施行されたについて解説します。

1.ガイドライン
令和6年3月に在留特別許可のガイドラインが変更になり、同年6月10日に入管法50条に創設された在留特別許可の申請手続きが施行されました。
そもそも在留特別許可とは何かというと、外国人が退去強制対象者に該当する場合でも、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、法務大臣は在留を特別に許可することができます。
この法務大臣による特別な許可を在留特別許可といいます。
(1)永住許可を受けているとき
(2)かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するとき
(4)難民の認定又は補完的保護の対象者の認定をうけているとき
(5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認められるとき
ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える実刑に処せられるなど一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者である場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮にかけると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可は認められません。
ここでの「特別な事情」とは、本邦で疾病の治療を受けている者で、相当な期間本邦で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがあることなど、在留を許可しないことが人道的見地からみて明らかに適切ではないとき認められる事情をいいます。
2.在留特別許可の性質
退去強制されるべき外国人について例外的・恩恵的に行われる措置であり、その判断は、法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられます。
在留特別許可をするかどうかは、個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断されます。
3.ガイドラインの内容
令和6年3月に在留特別許可のガイドラインが改定され、在留特別許可を認めるかどうかについていかなる事情が有利(積極要素)または不利な事情(消極要素)として認められるかが明示されました。以下どのような場合が積極要素となり、どのような事例が消極要素となるのかについて、解説していきます。
(1)在留許可の判断において有利(積極要素)となるものとして子の家族関係・家族とともに生活するという子の利益から積極的要素として認められるもの。
特に考慮する要素として、日本人又は特別永住者との家族関係
・当該外国人(在留特別許可を求める者)が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子であること
当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、
次のいずれにも当てはまること。
・当該実子が未成年かつ未婚であること、又は成年である者の身体的若しくは精神的障害により監護を要すること。
・当該実子と実際に相当期間同居し、当該実子を監護又は養育していること。
・当該外国人(在留特別許可を求める者)が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」の扶養を受けている未成年かつ未婚の実子であること
・当該外国人が「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」の実子をを扶養している場合であって、前記(1)の①及び②のいずれにも該当すること
・当該外国人が「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」と法的に婚姻している場合であって、夫婦として相当長期間共同生活をし、お互いに助け合って生活していて夫婦の間に子供がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること。
(2)素行について、積極要素として認められるもの
・当該外国人が日本の小中学校、高等学校で相当期間教育を受けているなどの事情により、現に相当程度に地域社会との関係が構築されていること、将来の仕事先が決まっていて雇用主等の第三者による支援が得られること、地域社会に溶け込み貢献している等の事情があること。
・当該外国人が、社会、経済、文化等の各分野において、日本に貢献し不可欠や役割を担っていること
(3)日本に入国することになった経緯において積極要素としてみとめられるもの
・入国のいきさつで人道上の配慮の必要性が認められる場合
特に有利となる積極要素として認められるもの
・当該外国人が、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であること。
・当該外国人が、難病等により日本での治療を必要としていること、またこのような治療を必要とする親族が日本にいて監護することが必要と認められること
・当該外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくても、出身国での情勢不安に照らして、当該外国人が帰国困難な状況にあることが客観的にあること
・当該外国人が、いずれの国籍又は市民権も有しておらず、入管法で定めたいずれの国ににも送還できないこと。
(4)人道上の配慮の必要性から特に考慮する積極要素としてみとめられるもの
・当該外国人が、難病等により日本での治療を必要としていること、またこのような治療を必要とする親族が日本にいて監護することが必要と認められること
・当該外国人が、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていなくても、出身国での情勢不安に照らして、当該外国人が帰国困難な状況にあることが客観的にあること
・当該外国人が、いずれの国籍又は市民権も有しておらず、入管法で定めたいずれの国ににも送還できないこと。
4.特に在留特別許可が認められなく方向になる消極的要素
(1)当該外国人が以下に掲げるような出入国管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反に及んだことがあること
・集団密航への関与や、他の外国人の不法入国を容易にする行為等を行ったことがあること。
・他の外国人の不法就労や、在留資格の偽装に関わる行為等をおこなったことがあること。
・在留カード等公的書類の偽変造や不正受交付、偽変造された在留カード等の行使、所持等を行ったこと
・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせるなど、日本の社会秩序を著しく乱す行為。
・当該外国人が、反社会的勢力であること他、消極的要素として判断されるものとして
・不法滞在の期間が長期に及んでいること
5.積極要素及び消極要素の考慮の在り方
在留特別許可の拒否の判断においては、個々の事案ごとに当該外国人の申立ての内容だけでなく、具体的根拠の有無や客観的な事情も考慮した結果、各考慮事情に認められる積極要素及び消極要素を総合的に勘案して、積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合には在留特別許可をする方向で検討されます。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が令和6年3月に改定された在留特別許可のガイドラインについて解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在留特別許可申請を取り扱っています。
在留特別許可についてのご検討の際は、是非こちらから弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
新設された「監理措置」とは何か

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「監理措置」制度について解説します。
1.監理措置について
2023年度の入管法の改正で,収容に代わる措置として「監理措置」(リンク先:出入国管理局)が新たに設けられ、2024年6月10日から施行されています。
監理措置とは、被収容者を監理人による監理の下で逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会の中で生活しながら退去強制手続きを進める措置です。
監理措置には、退去強制令書発布前のもの(法44条の2以下に規定)と退去強制令書発布後のもの(法第52条の2以下に規定)とがあります。
監理措置の目的は、全件収容主義の抜本的改善を図ることです。
監理措置が導入される前は、オーバーステイなどで在留資格のない者は原則収容の扱いとなり、これまで我が国で不法滞在にある者は原則として入管施設に収容する(全件収容主義)となっていたのを改め、主任審査官が個別案件ごとに逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮したうえで、被監理人に対して収容か監理措置かを判断します。
また収容の長期化を防止するため、収容されている者については、3か月ごとに必要的に収容を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入しました。
監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度については、本来の趣旨どおり、健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置としました。
監理措置の要件
退去強制令書が発布される前の監理措置の下で退去強制手続きを進める決定(以下「監理措置決定」)を受けるためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
(1)監理人が選定できること
(2)主任審査官が監理措置の決定を受ける外国人が逃亡又は証拠隠滅の恐れの程度等、諸般の事情を総合的に判断して、収容しないで退去強制手続きを行うことが相当と認めること。
2.監理人とは何か
監理人とは、監理人の責務を理解し、監理措置決定を受けようとする外国人の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行能力を考慮して適当と認められる者の中から、主任審査官が選定します(法44条3第1項又は法第52条の3第1項)。
(1)監理人の責務については(法第44条の3第2項から第5項まで又は法第52条の3第2項から第5項まで。)に規定されています。
・被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと
・被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を求めるように務めること
・主任審査官から報告を求められた時は、報告を行うこと
・法44条の3第4項・法第52条の3第4項が掲げる事由が発生したときは、事由が発 生したときから7日以内に届け出ること。
3.監理人の選定の取消・監理人の辞任について
主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときにその他監理人のその職務を継続させることが相当出ないと認めるときは、監理人の選定を取消すことができます(法第44条の3第6項又は法第52条の3第6項)。
また、監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに、主任審査官に届け出るように務めなければなりません(法第44条の3第7項又は法52条の3第6項)。
4.監理措置決定の取消しについて
(1)次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定を取消さなければなりません。
(法第44条の4第1項又は法第52条の4第1項)
・監理措置決定にあたり、保証金を納付することが条件とすることが条件とされる場合において、被監理者が納付期限までに保証金を納付しなかったとき。
・監理人の選定が取消された場合や監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
(2)次に掲げる事由に該当する場合は、監理措置決定が取消されることがあります。
(法第44条の4第2項又は法第52条の4第1項)
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
・被監理者が監理措置条件に違反したとき
・被監理者が主任審査官に対して必要な届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・被監理者が不法就労をしたとき(報酬を受ける活動の許可を受けずに働いた場合も含む)
5.報酬を受ける活動の許可について
在留資格のない外国人は、原則として働くことが認められていません。
ただし、退去強制令書発布前の被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先の指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労が認められることがあります(法第44条の5第1項)。
外国人の在留に関してお困りのことがある方,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせ,ご相談ください。
短期滞在と上陸拒否処分について
短期滞在と上陸拒否処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
上陸拒否される場合
最近日本人のハワイ上陸拒否が増加しているというニュースを目にします。
「犯罪者扱い」ハワイで日本人女性“入国拒否” 売春疑われる?若い女性から相談急増 テレ朝news
観光目的でハワイを訪問したが、入国審査でハワイへの上陸を拒否されそのまま送還されるというものです。
上陸拒否の事由はいくつかありますが、ニュースでは日本人がハワイへの上陸が拒否される理由の多くが、就労目的と思われていることからくるものが多いようです。
ハワイの空港到着時に、目立つ服装・滞在日数と比較して荷物に洋服が多い・自分の滞在先がよくわからない・滞在目的をうまく答えられない等、現地の入国審査官からハワイに来たのは観光目的ではなく、実は売春等違法な就労目的ではないか?との疑念を生じさせ、別室に呼ばれて再度なぜハワイに来たのか、ハワイした目的、滞在先、ハワイでの活動内容等を入国審査官に詳しく聞き取りされ、審査官からの質問にきちんと答えられないと不法就労を疑われて上陸拒否となります。
海外で日本人が不法就労を疑われる背景として、円安の影響により外貨を稼ぐため、日本と同じ仕事内容で日本の2倍~3倍の賃金がもらえることから、海外への労働目的での渡航が増加しており、特にハワイは日本人に人気であることから、現地当局は特に売春等の犯罪による不法就労を警戒しているということです。
外国人に対する入国審査が厳しいのは、アメリカだけではなく日本も同じです。
外国人に対する日本への上陸許可の要件については入管法で詳細に規定されています。
外国人が日本に入国するためには、原則として日本国大使館で取得した査証(ビザ)のある有効な旅券(パスポート)を所持したうえで、到着した出入国港において、入国審査官に対して上陸の申請を行い上陸拒否の証印を受けなければなりません。
我が国への入国を拒否される事由は入管法5条に列挙されており、具体的には以下のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
(1)保険・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸をみとめることが好ましくない者
(3)我が国から強制退去を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
(5)相互主義に基づき上陸を認めない者
上陸審査について
外国人が在留資格・在留期間が決まり日本に上陸するためには、原則として以下の通りの上陸のための条件を満たさなければなりません。(入管法第7条第1項)
①有効な旅券を所持すること
②査証が免除されている場合を除き、当該旅券に有効な査証を受けていること
③我が国において行う予定であると申請された活動が虚偽のものではなく、在留資格のいずれかに該当し、かつ、一部の在留資格については基準省令で定める上陸基準に適合すること
④申請された在留期間が法務省令の規定に適合すること
⑤上陸拒否事由に該当しないこと
観光や親族訪問目的で来日した外国人が、実は就労目的であると入国管理局から判断されて上陸拒否となったときに適用されるのは、③の条件に反すると判断された場合です。
(入管法7条1項2号)
本国の日本大使館からビザ(査証)を受けて適正な方法で日本に来たのにも関わらず、なぜ日本への上陸を拒否されるのか?全く理由が分からない、納得が行かない、正規の手続きを経てビザ(査証)を受けているのにいるのに空港内で足止めされて、空港内の入管施設に収容されるのは大変な人権侵害であり、理不尽極まりない、いったいどうなっているのか?という内容の相談を受けることがあります。
短期滞在での日本への上陸は、ビザ免除国を除いて、本国でビザ(査証)を受けることと日本上陸前の入国審査官の審査がセットになっており、例え有効なビザを取得していたとしても、入国審査の段階で日本国内へ上陸のための有効な条件を備えていることを入国審査官に認めてもらう必要があり、入国審査の際に、上陸のために必要な条件を満たしていないと入管から判断された場合には日本に上陸することができません。
入国審査の時に、入国審査官から日本への滞在目的、滞在先、滞在期間などの基本的事項については質問されたらきちんと答えられるように、あらかじめ準備しておくことが必要です。
また、家族訪問目的でビザを取得した場合で、日本の滞在期間が90日間ある場合、なぜ家族訪問で90日間必要なのか?90日間の活動日程を細かく聞かれるかもしれません。ここで90日間の活動予定を細かに説明するのが大変なので、入国審査官に「実は家族訪問だけでは凄く時間が余るので、友達のところで仕事の手伝いをしようと考えています」などと答えると、日本に上陸できずに2~3日空港内の入管施設に宿泊した後で本国に送還されることになります。
短期滞在は在留資格認定証明書での申請と違って、簡易な方法による在留資格であることから申請も容易であり、比較的に簡単に日本の滞在許可を得ることができます。
そのため短期滞在の申請人自身が、自分の日本での滞在目的や滞在期間、滞在先等を正確に覚えていないこともあり得ないことではなく、このような短期滞在での基本事項を入国審査官から質問されてきちんと答えられないような場合は、不法就労目的での来日を疑われて、日本への上陸を拒否される危険性が生じる恐れがあります。
上陸拒否処分となると日本に入国できず、本国に戻る費用も本人負担となります。
こうならないためには、短期滞在の申請においても実績のある入管専門の行政書士等にまかせて事前の対策をきちんと対策を取った方が、結果として安全で安く済むことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、短期滞在の在留申請手続きを扱っております。短期滞在で外国人の知人や親族を呼び寄せたい方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お著い合わせはこちらからどうぞ。